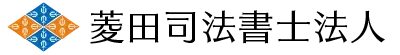ブログ
不動産を相続しても相続税がかからない方法とは?制度の仕組みと注意点を司法書士がわかりやすく解説|菱田司法書士法人(東京都大田区)

「不動産を相続したけれど、税金はどのくらいかかるのだろう?」
そんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。実は、不動産を相続しても相続税がかからないケースは決して少なくありません。
相続というと、「高額な税金が発生する」「不動産を受け継いだだけでも多額の支払いが必要」といったイメージを抱きがちですが、実際には相続税が発生しない人の方が多いのが現状です。ただし、税がかからないからといって、必要な手続きを行わなくていいわけではありません。
東京都大田区で90年以上の歴史を持つ菱田司法書士法人では、「不動産を相続したけれど、相続税がかからないのかどうか判断がつかない」「手続きをどう進めてよいかわからない」といったご相談を数多くいただいています。
相続には、登記や名義変更、遺産分割協議、他の相続人との調整など、税金以外にも重要なポイントが多数存在します。また、制度を正しく理解していないと、本来払わなくてよかったはずの税金が発生してしまうケースもあり得ます。
この記事では、不動産を相続しても相続税がかからない条件や仕組み、そして税がかからない場合でも必要な手続きや注意点について、専門家の視点からわかりやすく解説していきます。
「何となく不安」「何から始めればいいかわからない」という方こそ、この記事を参考にしていただき、相続に対する正しい知識と備えを得ていただければ幸いです。
目次
不動産を相続しても相続税がかからないって本当?

相続税がかからない人が多い理由
「不動産を相続すると、必ず相続税がかかる」と思っている方が非常に多くいらっしゃいます。ですが、実際には不動産を相続しても相続税がかからないケースのほうが圧倒的に多いという事実をご存じでしょうか?
これは、相続税の制度には一定額まで非課税となる“基礎控除”が設けられているからです。現在の相続税の基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で算出されます。たとえば、相続人が子ども2人の場合は、「3,000万円+600万円×2=4,200万円」が基礎控除額となり、この金額以下の遺産であれば相続税はかからないのです。
東京都大田区のような都市部であっても、築年数が経った住宅や評価額がそこまで高くない土地であれば、基礎控除内に収まる不動産も多く見受けられます。また、不動産だけではなく、預金や株式、生命保険などを合計した全体の遺産額で判断されるため、「不動産だけ相続した」場合には、税金が発生しないというケースが非常に多くあるのです。
しかし、相続税がかからないからといって安心してはいけません。必要な書類の整備や登記、分割協議などはしっかり行わなければならず、手続きを放置すると後々のトラブルにつながる可能性があります。
このような相続手続き全体を見据えたアドバイスと支援ができるのが、菱田司法書士法人(東京都大田区)です。法律・税務・登記を含む実務面を一体的にサポートし、ご家族の相続がスムーズに進むようお手伝いしています。
課税されるかどうかの判断基準
相続税がかかるかどうかの判断は、まず遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかが最初のポイントです。繰り返しになりますが、基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で算出されます。
また、不動産の評価額は固定資産税評価額や相続税評価額(路線価)などをもとに決まるため、実際の売却価格とは異なります。つまり、市場価格では高く見えても、相続税評価ではそれほど高くならない場合もあるのです。
このように、不動産を相続しても相続税がかからないかどうかは、正しい評価額の把握がカギとなります。評価があいまいなまま「税金はかからないだろう」と決めつけてしまうと、後から税務署から指摘を受けるリスクもあります。
判断に迷ったときは、不動産の評価に詳しい司法書士や税理士に相談することをおすすめします。特に、相続登記と評価額の整合性を確認するプロセスは、菱田司法書士法人のような専門家のサポートを受けることで確実に進めることができます。
相続税と他の税金の違い
「不動産を相続しても相続税がかからない」としても、他の税金が一切かからないというわけではありません。相続税と混同されやすいのが、固定資産税や登録免許税、不動産取得税などです。
たとえば、相続登記を行う際には登録免許税として不動産評価額の0.4%を納める必要があります。また、毎年の固定資産税も、名義を変更した相続人が支払うことになります。
しかし、これらは相続税とは性質が異なり、課税対象や計算方法も異なります。「税がかかる」とひとくくりにせず、どの税金に対して、どの手続きが必要かを正確に把握することが重要です。
菱田司法書士法人では、税理士とも連携して各種税金の概要を丁寧にご説明し、必要な支払い手続きや免除の対象についてもアドバイスしています。「何にどれだけお金がかかるのか」が見えないと不安な相続だからこそ、明確な情報と伴走支援が心強い味方になります。
税がかからないからといって放置してよいのか
「不動産を相続しても相続税がかからないなら、特に急がなくてもいいのでは?」と考えてしまう方も少なくありません。ですが、税がかからないことと、手続きをしなくてよいことはまったく別の話です。
とくに重要なのが、相続登記(名義変更)の義務化です。2024年からは、相続によって不動産を取得した場合、原則3年以内に登記しなければならないと法改正されており、違反すると10万円以下の過料が科される可能性もあります。
また、登記をしないことで将来の売却や活用ができなくなる、兄弟間でのトラブルが起きる、空き家問題に発展するといったリスクも現実に存在します。
相続税がかからないからこそ、比較的余裕をもって手続きが進められる状況でもあるため、早期の対応が最も効果的です。放置するのではなく、「今だからこそできる」ことに目を向けることが大切です。
菱田司法書士法人による初期サポートのご案内
菱田司法書士法人(東京都大田区)では、相続税がかからない相続にも丁寧に対応しています。私たちは、「税がかからないから簡単」という発想ではなく、「トラブルが起きにくい相続を設計する」という視点でサポートを行っています。
具体的には、以下のような初期支援を行っています。
- 不動産の正確な評価確認
- 登記簿の確認と名義人の特定
- 相続人の調査
- 必要書類の案内と収集支援
- 登記申請の代理
- 相続人同士の協議サポート
- 他士業(税理士・弁護士等)との連携窓口
税がかからない相続こそ、後回しにされやすいのが現実です。しかし、「かからない今」だからこそできる備えや対応を先に進めておくことが、将来の安心につながるのです。
相続に不安がある方、何から始めればよいかわからない方は、ぜひ一度、菱田司法書士法人にお気軽にご相談ください。どんな些細なことでも、私たちが“身近な法律家”として、誠実にお応えいたします。
相続税がかからないための仕組みと特例

基礎控除の活用方法
相続税が課税されるか否かの第一の判断基準となるのが「基礎控除」です。この制度があるおかげで、不動産を相続しても相続税がかからないケースが数多く発生しています。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。たとえば配偶者と子ども2人の3人が相続人であれば、「3,000万円+600万円×3=4,800万円」が非課税枠になります。
仮に被相続人が所有していた土地や建物の評価額がこの枠内であれば、どれだけ高価な不動産に見えても相続税は一切発生しないのです。これが、「不動産を相続しても相続税がかからない」と言われる最も基本的な理由です。
大田区のような都市部では、地価が高いエリアもあるものの、土地の面積や築年数によっては評価額が抑えられることも少なくありません。こうした評価額を正確に把握するには、専門家による精査が重要です。
小規模宅地等の特例とは?
不動産を相続する際に知っておきたいもう一つの大きな減税措置が、「小規模宅地等の特例」です。これは、相続する不動産が一定の条件を満たしていれば、その土地の評価額を最大80%まで減額できるという制度です。
たとえば、亡くなった方が住んでいた自宅を相続人が引き継ぎ、そのまま住み続ける場合、その敷地の評価額が80%減になる可能性があります。このような減額を適用すれば、相続税が大幅に軽減されるか、場合によっては完全に非課税になるケースもあるのです。
つまり、「不動産を相続しても相続税がかからない」背景には、このような特例制度の活用があるということです。ただし、適用要件には「被相続人の居住用不動産であること」「相続人が一定期間居住を継続すること」などの条件があり、一つでも満たしていなければ対象外になるため注意が必要です。
こうした判断を誤ると、本来受けられたはずの特例を見落としてしまい、余計な税金を払ってしまう恐れがあります。特例の活用こそ、専門家の知見と経験が求められる分野です。
配偶者の税額軽減制度
配偶者が不動産を相続する場合、さらに強力な免税措置が設けられています。それが「配偶者の税額軽減制度」です。この制度を使えば、配偶者が相続した財産が法定相続分以内、または1億6,000万円以下であれば、相続税は一切かかりません。
つまり、配偶者が居住していた自宅やその敷地を相続する際には、不動産を相続しても相続税がかからないどころか、高額の不動産であっても非課税になるケースが多く存在します。
この制度の特徴は、「申告することで適用される」という点にあります。税務署に黙っていれば自動的に適用されるわけではないため、必ず相続税申告書を提出し、軽減制度の適用を受ける必要があります。
菱田司法書士法人では、提携する税理士と連携し、相続税の軽減制度が最大限活用できるような申告体制を整えています。相続税がかからないはずだったのに「知らなかった」で済まされないトラブルを未然に防ぎます。
相続時精算課税制度の利用
「相続時精算課税制度」は、生前贈与と相続を組み合わせて税負担を軽減できる制度です。この制度を使えば、2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となり、相続時に合算して精算する形となります。
これにより、例えば不動産の持ち分を生前に子どもへ贈与し、相続時に残りの持ち分を引き継ぐことで、相続税がかからないように調整することも可能になります。
ただしこの制度は、一度選択すると通常の暦年贈与への変更はできず、メリットとデメリットの検討が必要です。また、相続時に不動産の評価額が想定より高くなった場合には、かえって税額が増える可能性もあります。
そのため、相続時精算課税制度の活用は、相続全体の設計を見据えた上での判断が求められる非常に繊細な対応です。
相続税がかからなかった実例紹介

都内戸建て住宅を相続したケース
大田区に住むA様は、父親が所有していた築30年の戸建て住宅とその敷地を相続しました。家族構成は母親とA様、妹の3人。父の遺産の大半がこの自宅不動産でした。
専門家による評価の結果、土地建物の相続税評価額は4,200万円。相続人3人の場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」。この基礎控除内に収まったため、不動産を相続しても相続税がかからないという結果になりました。
さらに、A様の母親がそのまま自宅に住み続けることにより、「小規模宅地等の特例」も適用でき、万が一評価額が高かった場合でも、税額がゼロまたは極めて軽微になる体制が整っていました。
事前に司法書士や税理士に相談していたことで、安心して手続きを進められた事例です。
二世帯住宅で配偶者が相続したケース
港区にお住まいのB様は、夫が他界したことにより、夫名義の二世帯住宅を相続しました。評価額は土地と建物で合計9,000万円と高額でしたが、B様は法定相続人として、配偶者の税額軽減制度を利用。
結果として、不動産を相続しても相続税がかからない状況を実現しました。さらに、子ども2人が残りの金融資産を分割で相続したことで、家族間での不公平感もなくスムーズな遺産分割が成立しました。
このように、特例制度を正しく適用すれば高額な不動産相続でも非課税になる可能性があることがわかる好例です。
築古アパートを兄弟で相続したケース
品川区で不動産経営をしていた被相続人のC様が亡くなり、築40年の木造アパートを兄弟2人で相続するケースがありました。建物の老朽化が進んでいたため、建物の評価額は低く、土地についても路線価を基にした評価で5,000万円程度に抑えられていました。
相続人が2人であるため、基礎控除は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」。評価額5,000万円との差額800万円に対しても、小規模宅地等の特例を活用することで、実質評価額が1,000万円以下となり、結果として相続税は非課税となりました。
この事例でも、「不動産を相続しても相続税がかからない」という現実があることを、身近に感じていただけるかと思います。
土地のみを相続し農地転用したケース
大田区郊外にある農地を相続したD様のケースでは、農地の評価額が固定資産税評価額に準じていたため、一般の宅地よりもかなり低く見積もられました。
D様は当初、「土地を相続すると相続税が大きくかかるのでは」と心配していましたが、実際には不動産を相続しても相続税がかからない結果となり、後に農地を宅地転用し、事業活用も実現しました。
評価の仕組みを理解していれば、土地の相続は大きなチャンスにもなり得るという好事例です。
専門家のサポートが重要な理由

手続きの漏れを防ぐために
相続の際には、遺産分割協議書の作成、登記の名義変更、税務申告など複雑な手続きが数多くあります。特に不動産が含まれる場合、その価値評価や登記はミスが許されない重要なポイントです。不動産を相続しても相続税がかからないように制度を活用するには、細かい条件を満たす必要があり、専門知識が不可欠です。
例えば、「小規模宅地等の特例」には厳格な要件があり、提出期限や書類不備があると特例が無効となり、多額の相続税が課されるリスクがあります。こうしたリスクを未然に防ぐためにも、司法書士のサポートが非常に重要です。
菱田司法書士法人では、大田区を中心に長年の経験から蓄積したノウハウで、あらゆるケースに対応できる体制を整えています。
税理士との連携で評価額を正しく調整
不動産の相続税評価は、実勢価格ではなく「相続税評価額」に基づいて行われます。しかし、その評価額をどのように算出するかによって納税額が大きく変わることもあります。
例えば、市場価格では8,000万円の不動産でも、路線価評価で5,000万円程度となる場合があります。この差が、不動産を相続しても相続税がかからない結果につながるのです。
司法書士が税理士と連携し、評価額の見直しや特例の適用の可能性を確認することで、依頼者にとって最も有利な相続手続きを提案することが可能になります。菱田司法書士法人では、信頼できる税理士とのネットワークを活かし、評価・税務・登記の一括対応が可能です。
分割と登記をスムーズに進める力
不動産を複数の相続人で分ける際には、誰がどの不動産を相続するか、また持ち分割合をどう設定するかなど、複雑な調整が必要です。このとき、感情的な対立や思い違いが起こりやすく、相続手続きが長引く原因になります。
司法書士は、中立な第三者として法的に有効な書類を作成し、トラブルを未然に防ぐ役割を担っています。また、登記の申請までワンストップで行えるため、手続きがスムーズに進みます。
特に、不動産を相続しても相続税がかからないようにするためには、特例の適用に必要な名義変更が遅れると制度が適用できない場合もあります。迅速かつ正確な対応こそが鍵となります。
曖昧な財産状況の「見える化」
相続では、不動産の価値だけでなく、預貯金や株式、負債までを含めた財産全体を明確にすることが大切です。被相続人が残した財産内容が曖昧なままでは、遺産分割の協議が進まず、トラブルの原因となります。
司法書士は、戸籍の取得や不動産登記簿の調査、公的証明書の取得を通じて、財産の全体像を明確にし、手続きを円滑に進めるための土台を築きます。
この「見える化」によって、どの不動産を誰が相続すれば、相続税がかからない形になるのかを具体的に検討できるようになります。
菱田司法書士法人のトータルサポート体制
東京都大田区に拠点を置く菱田司法書士法人は、相続に特化した法務のプロフェッショナルとして、書類作成・登記申請はもちろん、税理士や不動産会社との連携も含めた「トータルサポート」をご提供しています。
「誰に相談すればよいかわからない」「何から始めればいいかわからない」とお困りの方には、最初のご相談から相続完了まで一貫して寄り添う姿勢を大切にしています。
不動産を相続しても相続税がかからないように制度を最大限活用するために、私たちは一歩先を見据えたアドバイスをご提供します。
相続税の申告期限と対策のタイミング

相続税の申告は10ヶ月以内
相続が発生すると、相続税の申告と納付には期限があり、原則として「相続開始を知った日(=被相続人の死亡日)から10ヶ月以内」に完了しなければなりません。
この期限内にすべての相続財産の調査、評価、遺産分割協議、申告書の作成、納税までを済ませる必要があります。そのため、特に不動産が含まれる相続では早期の準備が欠かせません。
「不動産を相続しても相続税がかからない」状態を目指すには、この10ヶ月というタイムリミットの中で、評価や特例の適用を正確に判断し、漏れなく手続きを進めることが求められます。
遺産分割が終わらないと特例が使えないことも
例えば、「小規模宅地等の特例」は、申告時に遺産分割協議が成立していないと適用できないケースがあります。これは、不動産の所有者が明確になっていないと、税務署が特例を認められないためです。
そのため、遺産分割協議の長期化は避けるべきであり、専門家のサポートを受けながら速やかに協議をまとめる必要があります。
万が一10ヶ月を超えると、本来「不動産を相続しても相続税がかからない」はずだった相続でも、納税が必要になるリスクが生じるため注意が必要です。
事前対策が未来の安心につながる
相続税の対策は、「亡くなった後に考える」のでは遅く、生前の段階から対策を講じておくことが最も効果的です。具体的には、以下のような方法があります:
- 不動産の名義や登記内容の整理
- 生前贈与や信託制度の活用
- 遺言書の作成による分割トラブル防止
- 不動産の評価額の試算と特例の適用可能性の確認
こうした取り組みを通じて、「不動産を相続しても相続税がかからない」状況を作り出し、将来の相続人の負担を軽減できます。
菱田司法書士法人では、相続が発生する前の段階からご相談いただくことも歓迎しております。相続対策=資産を守るための計画です。
申告期限ギリギリでの相談では遅すぎることも
相続人の中には、「まだ時間があるから」と申告直前まで何も動かずに過ごしてしまう方もいます。しかし、10ヶ月という期限は意外と短く、いざ手続きを始めたときには間に合わないという事態も少なくありません。
また、不動産の評価や調査には一定の時間が必要であり、書類の取り寄せにも数週間を要する場合があります。加えて、相続人間の意見の相違などがあると、調整にも時間がかかるものです。
「不動産を相続しても相続税がかからない」はずだったのに、急いで処理したせいで特例を逃した…というような後悔を防ぐためにも、早めの行動が非常に重要です。
菱田司法書士法人による期限内完了支援
私たち菱田司法書士法人(東京都大田区)では、相続税申告の期限である10ヶ月を意識し、早期対応・迅速処理を徹底しています。
初回相談から登記・分割協議書の作成・専門家紹介(税理士、測量士など)までワンストップで支援し、「不動産を相続しても相続税がかからない」環境づくりに向けて全力でお手伝いいたします。
大切な資産を守るために、まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。
(Q&A)よくあるご質問にお答えします

Q1. 不動産を相続しても相続税がかからないケースは本当にあるのでしょうか?
A1. はい、実際にあります。 相続税には基礎控除があり、また配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用することで、不動産を相続しても相続税がかからないケースは数多く存在します。正確な評価と制度の理解が鍵になります。
Q2. 相続税がかからなかったとしても、相続登記は必要ですか?
A2. 必須です。 2024年からは相続登記の義務化により、相続発生から3年以内の登記が義務となりました。税金がかからなくても名義を変更しないと、不動産の売却や管理、再相続時に大きなトラブルの原因になります。
Q3. 評価額が高い都心の土地でも、非課税になる可能性はありますか?
A3. 条件次第では可能です。 たとえば、被相続人と同居していた配偶者が土地を引き継ぐ場合や、賃貸物件であれば貸家建付地の評価減が適用できる場合など、工夫次第で評価を大幅に下げられることがあります。
Q4. 遺産分割がまとまらない場合、どうすればいいですか?
A4. 早めに専門家へご相談ください。 協議が長引くと、相続税申告期限を超えたり、特例が使えなくなったりする恐れがあります。菱田司法書士法人では遺産分割協議書の作成支援や第三者としての調整役も行っております。
Q5. すでに相続が発生して10ヶ月が近いのですが、今からでも間に合いますか?
A5. 状況によりますが、早急な対応が必要です。 財産調査や評価、協議、申告など多くの工程があります。できる限り迅速にご相談いただければ、最大限サポートいたします。可能であればすぐにご連絡ください。
まとめ

不動産の相続は、単なる名義変更だけでは終わらない複雑な手続きが必要です。相続税評価や特例の活用次第で、不動産を相続しても相続税がかからないケースは少なくありませんが、それには的確な知識と判断が不可欠です。
本記事で解説したように、以下のような点が重要です:
- 基礎控除額や配偶者控除などの制度を把握すること
- 小規模宅地等の特例などを使って評価額を抑えること
- 評価額の高い不動産でも条件次第で非課税になる可能性があること
- 10ヶ月以内の申告期限を見据えた早めの行動が必要であること
こうした対応には、司法書士や税理士など相続の専門家と連携することが最も効果的です。
菱田司法書士法人(東京都大田区)では、相続開始前からの相談はもちろん、急な相続や相続人同士の意見調整まで幅広く対応いたします。
「不動産を相続しても相続税がかからない方法が知りたい」「相続登記をスムーズに済ませたい」とお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
人生で何度も経験することではないからこそ、安心して任せられる専門家と共に、未来への一歩を踏み出しましょう。