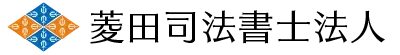ブログ
兄弟で相続する不動産の正しい分け方と注意点|菱田司法書士法人

家族が亡くなった後、遺された財産をどう分けるかという「相続」の問題は、誰にとっても避けて通れない現実です。中でも、不動産の扱いは特に複雑で、分割の難しさや維持管理の負担、感情的な対立を引き起こしやすい要素を多く含んでいます。
さらに、相続人が兄弟である場合は、幼い頃からの関係性や親への貢献度、生活状況の違いなどが影響し、話し合いが難航するケースも少なくありません。「誰が住むのか」「どう分けるのか」「売却するのか」などの判断を巡り、兄弟間の意見が食い違うことは非常によくある相談内容です。
特に不動産を共有するかどうかという判断は、将来的なトラブルのリスクを左右する大きなポイントとなります。名義変更をせずに放置することで、所有者不明土地となり、相続人全員が不利益を被る可能性もあるのです。
私たち菱田司法書士法人(東京都大田区)では、こうした相続の場面において、法的な正確さとご家族の感情の両面に配慮したサポートを行っています。司法書士として登記や手続きを担うだけでなく、不動産の価値や地域性、兄弟間のバランスに配慮した分割方法の提案なども含め、総合的なご支援が可能です。
この記事では、「相続」「不動産」「兄弟」という3つの視点から、よくある悩みや解決策を丁寧に解説していきます。相続手続きを始めるにあたって何を準備すればよいのか、どのように兄弟と協力すべきか、不動産をどう扱えばよいかといった実務的な情報を中心に、トラブルを防ぎ、家族みんなが納得できる相続の進め方をご紹介します。
ご家族の大切な資産と関係を守るために、ぜひ本記事をお役立てください。
相続で兄弟が不動産を共有する現実

兄弟間での不動産相続が増えている背景
日本全体で高齢化が進む中、相続に関する相談は年々増加しています。そのなかでも、実家や土地といった不動産を相続したい、あるいは整理したいという兄弟同士の相談が特に目立つ傾向にあります。
背景には、核家族化や都市部への転居、空き家の増加といった社会的な変化があり、「親の家を誰が受け継ぐのか」というテーマは、全国どこでも起こり得る現代的な課題となっています。
兄弟が複数いる場合、それぞれが異なる生活環境にあり、「実家に戻りたい」「売却して現金化したい」「残しておきたい」といった思いが交錯しやすいのが実情です。相続人が多ければ多いほど、意見の調整に時間と労力がかかるのは避けられません。
また、不動産は現金とは異なり、そのままの形で分割することが難しい財産です。たとえば、東京都大田区のように地価の高い地域では、一つの土地や建物を公平に分けることが困難なケースも多く、売却か共有かといった選択が迫られる場面も出てきます。
こうした複雑な状況に直面したときこそ、法律と現実の両方を知る専門家のアドバイスが不可欠です。菱田司法書士法人では、相続に関する不安や兄弟間の調整に悩む方へ向けて、不動産を中心とした相続サポートを丁寧にご案内しています。
不動産の共有とはどういう状態か
相続の現場で「とりあえず共有名義にしておこう」という選択をするケースは少なくありません。これは、兄弟全員が相続人である場合、特定の一人に譲るよりも“公平に思える”選択肢として受け入れられやすいからです。
しかし、共有名義とは、一つの不動産に対して複数人が持分を持つという状態を意味し、不動産を売却するにも修繕するにも、全員の同意が必要になります。つまり、一人の意思だけで自由に動かせない財産となってしまうのです。
たとえば、兄が1/2、弟が1/2の持分で共有している家を売却しようとしても、どちらか一方が反対すれば話が進みません。さらに、共有者の一人が亡くなれば、その持分をさらに新たな相続人が受け継ぐこととなり、共有関係が複雑化しやすいのも大きな問題点です。
不動産の共有は、一時的な措置には向いていますが、長期的な維持にはリスクが伴うということを念頭に置く必要があります。
不動産共有が引き起こすリスク
兄弟で共有した不動産は、時間が経つほどに問題が表面化しやすくなります。たとえば、「誰が固定資産税を支払うのか」「空き家の管理を誰が担当するのか」「修繕費はどうするのか」といった責任や負担の所在が曖昧になりがちです。
また、一方の兄弟が実家に住み続け、もう一方が離れて暮らしているという状況では、利便性や公平性に対する不満が蓄積されることもあります。「自分は何も使っていないのに、なぜ費用を負担しなければならないのか」といった感情的な対立が起こりやすいのです。
さらに、共有名義のままでは、売却や賃貸といった資産活用が難しくなり、相続後の財産管理が滞るリスクも高くなります。こうしたリスクを未然に防ぐためにも、共有の状態を放置せず、早めに分割や売却などの対策を講じることが大切です。
揉めやすい兄弟間相続の具体例
相続をめぐる兄弟間のトラブルは、現場で頻繁に起きている身近な問題です。たとえば、「長男が実家に住み続けており、売却を拒否している」「次男が遠方に住んでいて、管理や費用を任されていない」など、立場や状況の違いから不満が生まれるケースが非常に多いのです。
また、親が生前に「この家は長男にやる」と口頭で言っていたとしても、遺言書がない限りは法的な効力がなく、兄弟全員の協議が必要になります。こうした曖昧な「思い込み」が、実際の遺産分割時に大きな争いを生む原因になることもあります。
不動産の扱いが話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を経る必要があり、時間も費用もかかります。トラブルを未然に防ぐためには、専門家が第三者として冷静に関わることが有効な対処法となります。
菱田司法書士法人ができる相続の初期サポート
菱田司法書士法人では、相続開始直後からの相談を通じて、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供しています。まずは、誰が相続人で、どのような不動産が含まれているかという現状整理から始め、相続登記の必要性や名義変更の方法、兄弟間の話し合いの進め方まで、わかりやすくご説明いたします。
さらに、東京都大田区の地域特性や不動産事情に熟知しているため、実勢価格や将来的な活用法も含めて、現実的かつ納得のいく分割方法をご提案することが可能です。
必要に応じて、税理士・弁護士・不動産会社などとの連携体制を整えており、ワンストップでの相続支援を実現しています。書類の作成から登記手続き、協議書の内容確認まで、すべて司法書士が責任をもって対応します。
「相続は難しそうだから…」と後回しにしてしまう前に、まずは私たちにご相談ください。不動産の相続に関するご不安や兄弟間の調整について、一つひとつ丁寧に寄り添いながらサポートいたします。
不動産を兄弟でスムーズに相続する方法

相続開始前にしておくべき準備とは
相続が発生してから動き出すのでは遅いケースも少なくありません。特に不動産のように価値が高く、分けにくい財産がある場合は、生前の準備が円満な遺産分割の鍵となります。
まず重要なのは、被相続人となる親や祖父母の考えを生きているうちに確認しておくことです。「この不動産は誰に残したいのか」「売却を希望するのか」「共有を避けたいのか」など、本人の意向を兄弟で共有しておくことが、のちのトラブル回避につながります。
また、名義や登記の現状を確認しておくことも非常に大切です。登記簿上の所有者がすでに亡くなっていたり、古い住所のままになっていたりすると、相続登記が煩雑になってしまいます。
加えて、遺言書があるかどうかの確認も忘れてはなりません。遺言書の有無や内容によって、遺産分割協議が必要かどうかが変わってきます。特に兄弟が複数いる場合、意思の統一は時間がかかるため、早い段階から話し合いを始めることが重要です。
菱田司法書士法人(東京都大田区)では、相続前の事前相談を多数受けており、「いま何をすべきか」「どう準備すべきか」について丁寧にご案内しています。不動産の所在確認や権利関係の調査、兄弟間での意見調整に至るまで、包括的なアドバイスをご提供いたします。
相続が「争続」にならないために。事前準備こそが、家族を守る最大の安心材料となるのです。
遺言書の活用と注意点
兄弟間の不動産相続で最も有効な対策のひとつが「遺言書の作成」です。法的に有効な遺言があることで、誰に何を渡すかが明確になり、相続人同士の衝突を未然に防ぐ効果があります。
特に不動産は分けにくいため、「長男にこの家を、次男には預貯金を」といった明確な意思表示があれば、兄弟間での混乱を防ぐことができます。
ただし、遺言書には法律上の要件があり、要件を満たさないと無効になるリスクもあります。自筆証書遺言の場合は、日付・署名・押印・全文自書などが必要であり、少しのミスで全体が無効と判断されることもあるのです。
そのため、確実性を求める場合は「公正証書遺言」の作成がおすすめです。菱田司法書士法人では、遺言内容の相談から公証人との連携まで、ワンストップでお手伝いしています。
生前贈与とそのリスク
相続前に不動産を生前贈与するという選択肢もあります。たとえば、実家に住む予定の兄に事前に家を贈与しておくことで、相続時の争いを防ぐというケースです。
しかし、生前贈与には注意点も多く、一定額以上の贈与には高額な贈与税が課せられる可能性があります。また、他の兄弟から「自分だけ優遇されている」と不満が生じれば、遺留分侵害請求などの法的対応を受けるリスクもあるのです。
さらに、生前に贈与した不動産も「特別受益」として相続財産に含まれる場合があるため、相続時に再計算される可能性も考慮しなければなりません。
菱田司法書士法人では、贈与にともなう登記の手続きやリスクのご説明を丁寧に行い、各家庭に合わせた最善の方法を一緒に検討しています。
遺産分割協議書の作成ポイント
不動産を含む相続を行う場合、遺産分割協議書の作成は欠かせません。これは、相続人全員が話し合い、「誰が何を受け取るか」を決定し、書面として残すためのものです。
兄弟全員の署名と実印が必要で、印鑑証明書の添付も求められます。この協議書がなければ、不動産の相続登記が進められず、名義変更ができません。
内容は正確かつ明確である必要があり、特に不動産の所在や登記簿上の情報を間違えると、再作成が必要になることもあるため、注意が必要です。
菱田司法書士法人では、法的に有効で争いを招かない協議書の作成を全面的に支援し、兄弟全員が納得できる形に整えることを第一に考えて対応しています。
東京都大田区の相続サポートの活用
東京都大田区では、都心と住宅地が混在するエリア特性上、相続された不動産の価値や活用法も多種多様です。実家のある地域の将来性や再開発計画、周辺相場などを踏まえた上で、どのように相続すべきかを判断することが求められます。
また、兄弟で話し合いを進めるにあたって、地域に根差した司法書士が間に入ることで、よりスムーズかつ円満な分割が実現しやすくなります。
菱田司法書士法人は、1933年の創業以来、大田区の地域事情に精通し、数多くの相続・不動産関連の実務を積み重ねてきた専門事務所です。単なる登記や書類作成にとどまらず、各家庭の思いや事情に寄り添った相続のサポートを心がけています。
「兄弟で揉めたくない」「不動産をどう扱えばよいかわからない」――そんなお悩みをお持ちの方こそ、私たちのような地元密着の専門家にご相談ください。誠実に、そして丁寧に、ご家族が安心できる相続を一緒に考えてまいります。
不動産の評価と分け方の実際
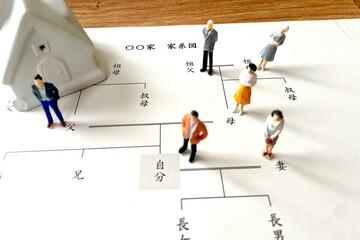
不動産の評価方法と分け方の考え方
相続手続きにおいて、不動産の評価は避けて通れない重要なプロセスです。なぜなら、不動産は現金のように簡単に分割することができず、正確な評価がなければ、兄弟間での公平な分割が困難になるためです。
不動産の評価にはいくつかの指標があります。たとえば、固定資産税評価額、相続税評価額、路線価、実勢価格(市場価格)などが代表的なものです。これらの金額は一つに統一されているわけではなく、目的によって使い分ける必要があります。
実際の分割を考える際には、実勢価格が最も現実に即した指標となることが多く、売却時や代償分割の判断基準として活用されます。たとえば、東京都大田区のように地価の高い地域では、わずかな差で何百万円もの差額が生じることもあり、評価の正確性が相続人の納得度に直結します。
兄弟で相続する際、不動産の評価に対する認識の違いが対立の原因になることもあります。「この家はもっと高く売れる」「思い出があるからお金では計れない」など、主観が交じると冷静な協議が難しくなることもあるのです。
菱田司法書士法人では、司法書士の視点に加え、必要に応じて不動産会社や不動産鑑定士と連携し、適正な評価をご提案。それをもとに、兄弟全員が納得できる分割案を設計するサポートを行っています。法と実情の両方を見据えた評価だからこそ、公平性を保つことが可能なのです。
売却して現金分割するメリット・デメリット
不動産を兄弟で分ける際、「売却して現金で分割する」という選択肢は、比較的トラブルが少なく公平感を得やすい方法のひとつです。
この方法の最大のメリットは、明確な金額で分けられるため、感情的な対立が生じにくいことです。不動産を現金化することで、各相続人が自由に使える資産として受け取れる点も魅力です。
一方で、デメリットもあります。たとえば、売却に時間がかかる、購入希望者が現れない、思ったほど高く売れないなど、状況によっては希望通りの分割が実現しないこともあります。また、実家に思い入れのある兄弟にとっては、「売る」という選択自体に強い抵抗感を抱くこともあります。
不動産の売却と現金分割は、兄弟間の温度差を丁寧に埋めながら進める必要がある選択肢です。
代償金や交換による分け方
不動産を誰か1人が相続し、他の兄弟には代償金を支払う「代償分割」は、実務上非常に多く用いられている方法です。これにより、共有名義による将来的なリスクを回避しつつ、他の兄弟の相続分を金銭で公平に保証することができます。
この方法は特に、「実家に住んでいる長男が不動産を取得し、次男には現金で代償金を支払う」といったケースに適しています。代償金の算出には、不動産の評価と相続人間の合意が不可欠となるため、第三者が間に入り、客観的な調整を行うことが有効です。
また、「自宅は兄、別荘は弟」といった不動産同士の交換による分割も選択肢の一つですが、それぞれの価値や維持費、将来の利用計画も考慮して判断すべきです。
共有名義で所有する場合の注意点
不動産を兄弟で共有名義にすることは、一見“平等”に思える方法ですが、実際には数多くのリスクを含んでいます。たとえば、売却や建て替えなどの際には共有者全員の同意が必要であり、一人でも反対すれば手続きが進まない状態に陥るのです。
また、共有者の一人が亡くなった場合、その持分はさらに別の相続人へと分散され、相続関係がどんどん複雑化していく危険性もあります。このような状態が放置されると、不動産の利活用はもちろん、管理や税務面でも大きな負担となります。
「仲が良いから大丈夫」と思っていても、数年後にはそれぞれの事情が変わり、意見が食い違うことは珍しくありません。そのため、共有名義は最終手段と考え、できる限り単独名義や代償分割などを検討することが望ましい選択です。
菱田司法書士法人による評価と分割のサポート
菱田司法書士法人(東京都大田区)では、不動産の評価から分割までを一貫してサポートできる体制を整えております。まずは、登記簿や公図をもとに、対象となる不動産の基本情報を整理します。そこから、地価・路線価・固定資産税評価額などを参考にしながら、実勢に即した評価を導き出し、兄弟間の分割協議の土台となる数値を提示します。
さらに、評価額に基づいて代償分割の試算、共有か単独取得かの判断、売却の可否など、複数の選択肢をご提案。状況に応じて、不動産会社や税理士と連携しながら、実務的かつ法的に問題のない方法で進行します。
私たちは単なる手続き代行者ではありません。兄弟間の関係性、将来の維持費、感情面のケアといった“目に見えない要素”まで考慮し、納得と安心を得られる相続をお手伝いする専門家です。
「相続では、相手の気持ちを尊重しつつ、自分も不利益を被らないようにしたい」――その両方を実現するためのパートナーとして、菱田司法書士法人をお選びください。
兄弟間でトラブルが起きたときの対応

揉めた場合の調停・審判の流れ
相続をきっかけに、兄弟間で関係が悪化してしまうケースは決して珍しくありません。特に不動産が絡む場合は、分け方や使い道、価値の認識にズレが生じやすく、感情的な対立に発展する可能性が高まります。
このように、話し合いが平行線をたどると、家庭裁判所での「遺産分割調停」や「審判」に進むことになります。調停では、中立の立場である裁判所の調停委員が間に入り、相続人全員の意見を聞きながら合意形成を促進します。
調停で合意が成立すれば、その内容は調停調書に記載され、法的拘束力のある取り決めとして機能します。しかし、調停でもまとまらなかった場合は、審判に移行し、家庭裁判所が一方的に分割方法を決定することになります。
ただし、審判では個々の感情や家庭事情が十分に反映されない場合もあり、後悔や不満が残る結果になることもあるため、できる限り調停の段階で解決を目指すことが望ましいでしょう。
菱田司法書士法人(東京都大田区)では、調停や審判の申立てに必要な書類作成から、法的手続きの進行管理、専門家との連携まで一貫して対応可能です。早い段階でのご相談により、家庭裁判所に持ち込まずに済むケースも多くあります。
家庭裁判所での分割調停について
家庭裁判所での調停は、兄弟同士での相続トラブルを法的に整理するための仕組みです。当事者だけでの話し合いが困難になったとき、裁判所が間に入って冷静な場で合意を目指すことができます。
調停では、不動産の価値や権利関係、過去の相続手続きの履歴なども考慮され、公平な提案がなされます。特に、「誰が不動産を相続するか」「代償金は必要か」「兄弟間の分担はどうするか」といった実務的な話が中心となります。
調停成立後は、その内容が調書として確定し、登記手続きや支払い義務などにも法的効力を持たせることができます。
兄弟間で感情的対立があるときの仲介方法
不動産の相続において、兄弟間のトラブルは“法律の問題”というより“感情のもつれ”であることが多いのが現実です。「介護をどちらがしていたか」「親に可愛がられていたのは誰か」「昔の不満が解消されていない」といった背景が、財産の話になると一気に噴き出すことがあります。
そうした場合には、司法書士などの中立的な専門家が入ることで、感情のぶつかり合いを和らげながら、事実に基づいた調整を行うことが有効です。法律に詳しくない方でも理解できるよう、第三者が論点を整理してあげることで、冷静な対話の場が生まれます。
菱田司法書士法人では、兄弟間の話し合いの同席や、意見調整の助言など、心理面の配慮を含めたサポートも実施しています。
相続放棄・代償分割などの対処法
相続トラブルを避けるための選択肢として、「相続放棄」や「代償分割」の活用が挙げられます。
まず、相続放棄は家庭裁判所に申述することで、その人が相続人でなくなる方法です。借金などの負債が多い相続では有効な手段ですが、不動産などのプラス財産も一切相続できなくなる点には注意が必要です。
一方の代償分割は、ある相続人が不動産を相続し、他の兄弟にはその分の代償金を支払うことで公平性を確保する方法です。共有を避けながら、実務的かつ納得感のある分割を目指せるメリットがあります。
どちらの方法も、法的な知識と適切な準備がなければ進めるのが難しいため、事前に司法書士へ相談し、最適な方針を一緒に検討することが重要です。
菱田司法書士法人が行う中立的調整サポート
菱田司法書士法人は、相続をめぐる兄弟間の調整支援に長けた司法書士事務所として、東京都大田区を中心に多数の相談実績があります。不動産をどう分けるか、共有を避ける方法はあるか、誰が名義を持つべきか――そうした実務的な問題と同時に、ご家族の感情にも寄り添った調整を心がけています。
具体的には、相続人それぞれの立場や考えを中立的にヒアリングし、感情の対立を最小限に抑えながら、合意形成に必要な論点を整理。必要であれば、協議書の作成・登記の準備・他士業との連携などを一括対応することで、時間と手間の大幅な軽減を実現します。
また、「一人で話し合いに参加するのが不安」「相手と直接話すのを避けたい」といったご相談に対しても、同席・代行・文書作成など柔軟に対応できる体制を整えています。
相続・不動産・兄弟――この3つの要素が交わる場面では、法的知識と人間関係の調整力の両方を持つ専門家が不可欠です。私たちは、「分けること」だけでなく、「残すべき関係」を守る相続支援を目指し、ご家族にとって最良の結果を導くために尽力しています。
相続不動産を放置する危険性と対策

相続登記の義務化と罰則について
これまで、不動産の相続登記は義務ではありませんでした。しかし、所有者不明土地の問題が深刻化したことを受け、2024年4月から相続登記が義務化されました。これは、相続によって不動産を取得した場合、原則3年以内に登記を行わなければならないという制度です。
義務を怠った場合には、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。つまり、「兄弟とまだ話し合いがまとまっていない」「とりあえず様子を見ている」という状態では済まされない時代になったということです。
特に、複数人で不動産を相続する兄弟間では、登記手続きが後回しにされる傾向があります。しかし、それにより他の手続きが進まず、税務や管理面での支障も大きくなります。
菱田司法書士法人(東京都大田区)では、義務化に対応した迅速な登記手続きをサポート。登記に必要な書類の取得・作成から、兄弟間の意見調整まで、専門家としてスムーズな進行をお手伝いしています。放置せず、早めの対策が将来の安心へとつながります。
放置が引き起こす空き家問題
不動産を相続したものの、誰も住まないまま放置されると「空き家問題」へと発展します。全国的にも空き家の増加は深刻で、特に高齢の親から相続された実家がそのまま放置されているケースが非常に多いのが現状です。
空き家は景観の悪化や治安の低下、倒壊リスクなど、近隣住民に対する社会的な悪影響をもたらす可能性があるため、各自治体が管理を強化しつつあります。固定資産税の軽減措置が外される場合もあり、経済的な負担が重くのしかかることもあります。
兄弟間で「誰も住まないからそのままで…」と話が進まないまま放置してしまうと、結果的に誰も得をしない状況に陥ります。こうしたリスクを防ぐには、不動産の将来像を兄弟で共有し、活用または処分について具体的に話し合うことが必要です。
再開発や売却時の障害
東京都大田区のような都市部では、再開発や都市整備の計画により、不動産の売却や立ち退きが必要になることがあります。しかし、相続登記がされていない不動産や共有名義のままの物件では、こうした流れにスムーズに乗ることができません。
登記がされていない場合、法的な所有者が不明となり、自治体や買主との交渉がストップする可能性があります。また、兄弟のうち一人でも連絡が取れなかったり、同意が得られなかったりすると、売却の機会そのものを失うこともあるのです。
相続をきっかけに得たはずの資産が、活かされないまま“塩漬け”になるのは非常にもったいない状況です。不動産を将来の財産として活用するためにも、登記や分割の整理は早期に進めておくことが重要です。
管理責任や税金負担の実態
相続した不動産を放置すると、管理責任と税金の負担という2つの大きな義務がのしかかってきます。たとえば、老朽化により瓦が落下した、倒壊した、火災が起きたなどの場合、所有者として責任を問われる可能性があるのです。
また、固定資産税は名義が変更されていない場合でも、納税義務は相続人に発生します。兄弟のうち誰かが代表して支払っているケースでは、「自分だけ負担している」といった不満の原因になることも少なくありません。
さらに、放置によって税金が滞納された場合、延滞金や差し押さえといった法的リスクに発展する可能性もあります。不動産を保有する以上、“放っておく”という選択肢は現実的ではないのです。
東京都大田区で相続を放置しないために
東京都大田区には、利便性の高いエリアから閑静な住宅街まで、さまざまな特性をもつ不動産が存在しています。この地域の不動産は、相続後の活用方法によっては、大きな資産価値を生む可能性を秘めているのです。
しかしその一方で、高額な固定資産税や築年数の経過による劣化管理の問題など、放置によるリスクも大きいため、相続が発生した際には早めに対応することが肝要です。
菱田司法書士法人では、大田区内で多くの相続・不動産関連の相談に応じてきた経験を活かし、地域の相場や不動産特性を踏まえた実践的な提案が可能です。登記の専門知識はもちろん、兄弟間のバランスを配慮した対応、各種士業との連携、空き家対策や売却支援もワンストップでご提供します。
「忙しくて手が回らない」「兄弟と話し合う時間がない」――そうした声に対し、私たちは“代わりに考え、代わりに動く”パートナーとして全力でお応えします。
不動産の相続を放置することは、ご家族の未来に不安を残す選択です。今のうちに、正しい手続きを、正しい順序で進めることが、安心と信頼を築く第一歩になります。
Q&A:よくある7つのご質問

Q1:相続登記の期限を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?
相続登記には3年以内という期限がありますが、過ぎてしまってもすぐに手続き可能です。ただし、過料(罰金)の対象となることがあるため、できるだけ早く司法書士にご相談ください。
Q2:兄弟の一人が相続放棄を検討しています。遺産分割協議はどうなりますか?
相続放棄が認められると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。残った兄弟だけで協議を進め、不動産の分割方法や登記手続きを再調整する必要があります。
Q3:不動産を売却したいが、兄弟の同意が得られません。対処法は?
共有名義の不動産は、売却に全員の同意が必要です。どうしても合意が得られない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停を利用し、法的に解決を図ることができます。
Q4:公正証書遺言を作成すべき理由は何ですか?
自筆証書遺言は形式不備で無効になるリスクがあります。公正証書遺言は公証人役場で作成し、法的要件を満たすため安心です。
Q5:代償分割で支払う代償金の目安はどう決めればよいですか?
代償金は、不動産の実勢価格を基準に算出します。評価額に基づき、相続人間で公平な金額を話し合い、協議書に数値を明確に記載することが重要です。
Q6:空き家リスクを避けるためには何から始めるべきですか?
まずは相続登記を完了し、所有者を明確にしたうえで活用計画を立案しましょう。賃貸や売却、建て替えなど、選択肢を兄弟で共有し、早めに意思決定することがポイントです。
Q7:共有名義のまま相続した不動産を管理するコツは?
固定資産税や修繕費は持分に応じて明確に負担割合を決定し、定期的に兄弟間で会議を設けるなど、コミュニケーションの仕組みを整えると良好な関係を維持できます。
まとめ

不動産の相続は、法律だけでなく家族間の信頼関係にも大きく関わる重要なテーマです。特に兄弟が複数いる場合は、「誰がどの不動産を取得するか」「共有か単独名義か」「代償金の有無」など、多岐にわたる調整事項が発生します。
東京都大田区の不動産事情に精通した菱田司法書士法人では、相続登記の義務化対応から、遺言書作成、生前贈与、代償分割、調停手続きまで、あらゆるステージでワンストップのサポートを提供しています。兄弟間の対立を未然に防ぎ、公平かつ納得のいく相続を実現するためのパートナーとして、ぜひご活用ください。
「相続」「不動産」「兄弟」という複雑な組み合わせだからこそ、専門家の中立的な助言と手続き支援が、家族の安心と未来を守る鍵となります。まずはお気軽にお問い合わせいただき、ご家族全員が納得できる相続のかたちを一緒に考えてまいりましょう。