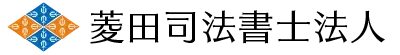ブログ
相続で共有になった不動産をどう整理する?|菱田司法書士法人

相続において「共有」の状態になる不動産が増えています。たとえば、親から土地や建物を引き継いだ際、兄弟姉妹など複数の相続人で名義を持つことになり、その不動産が共有名義となるケースが一般的です。
しかし、この「共有」は、相続人間の公平を保つ手段である一方で、現実にはさまざまな問題を引き起こす原因となることがあります。不動産を共有していると、売却や賃貸、修繕などの際にすべての共有者の合意が必要となり、思ったように活用できないことが多くあるのです。
さらに、名義人の一部が遠方に住んでいたり、高齢で意思確認が難しかったりする場合、手続きが遅延し、不動産そのものの資産価値や利便性が損なわれるリスクもあります。こうした共有状態を放置することで、家族間の関係悪化や相続トラブルへと発展する可能性も否定できません。
菱田司法書士法人(東京都大田区)では、相続後に発生しやすい不動産共有の問題について、登記や遺産分割の観点から総合的にサポートしております。創業90年以上の歴史を持つ当法人は、相続に関する法的手続きに精通しており、地域の皆さまに寄り添った解決策をご提供しています。
本記事では、不動産を相続した際に「共有」になる仕組みやリスク、その解消方法や予防策までを、具体的にわかりやすく解説してまいります。今まさに相続を検討中の方や、不動産の共有名義でお困りの方にとって、実務的なヒントと安心への第一歩となる内容をお届けします。
不動産を共有で相続するとは

相続と不動産共有の基本構造
相続が発生した際に不動産を複数人で所有する状態が「共有」です。これは、法定相続分に従って権利が分配される仕組みによるものです。たとえば、配偶者と子ども2人が相続人となった場合、それぞれの法定割合に基づいて、不動産の所有権を共有することになります。
この「共有」は、権利の上では分けられても、現物としての不動産は分割できないために生じます。つまり、土地や建物といった実体を分けることができない以上、登記上では名義を共有にするしかないのです。
問題は、その共有状態が将来的にどう影響するかという点にあります。共有名義の不動産は、所有者全員の合意がなければ原則として売却も賃貸もできません。また、登記上の共有持分と実際の利用状況が一致していないことも多く、不公平感やトラブルの温床となるのです。
このような理由から、不動産を相続したときに共有とするかどうかは慎重に判断する必要があります。
共有名義になるケースと背景
不動産が共有となる背景には、いくつかの典型的なパターンがあります。もっとも多いのが、遺言が存在せず、法定相続分に基づいて分割されるケースです。遺産の中に現金や有価証券が少なく、実物不動産しかない場合、分ける方法がなく、やむなく共有にせざるを得ない状況が生まれます。
また、相続人間で「今後売却するかどうか決まっていない」「まだ住む人が決まっていない」といった理由から、とりあえず共有名義にしておくという判断も少なくありません。しかしこの“とりあえず”が、後のトラブルの火種となることはよくあります。
共有状態を望まなかったとしても、相続の現場では時間が限られている中で判断を迫られることも多く、十分な検討を経ないまま共有登記されるという実態があるのです。だからこそ、事前の準備や専門家のサポートが重要になります。
登記されていない共有の問題点
共有という状態は、正式に登記を行わなければ第三者に対して主張することができません。相続手続きの一環である登記を怠ってしまうと、不動産の名義が亡くなった方のままになり、法的なリスクを伴います。
たとえば、登記されていない共有不動産は、相続人の一人が勝手に使用したり、他人に貸したりしても、それを止める法的な力が弱いという現実があります。また、登記が未了のまま年月が経過すると、次世代の相続が発生し、共有者の数が膨れ上がってしまうという重大な問題も起こります。
このような「名義放置」は、結果的に相続人の権利を曖昧にし、共有不動産が“使えない資産”として眠ってしまうことにもつながります。不動産を相続したならば、まず登記を行い、所有権を明確にすることが第一歩です。
放置された共有不動産の実例
実際に相続後に共有状態となった不動産が放置された結果、深刻な問題に発展した例は数多くあります。たとえば、兄弟3人で親の土地を共有したまま10年が経過し、その間に1人が亡くなったことで、その相続人である子どもたちが新たな共有者になってしまった、というケースです。
このようにして、本来は3人だった所有者が10人以上に増えてしまい、誰がどう管理するかも不明確になり、結局は空き地や空き家として放置されてしまうのです。こうした状況は、固定資産税の未払い、建物の老朽化、近隣トラブルの発生などを引き起こす可能性があります。
東京都大田区のような都市部では、再開発の妨げになることもあり、行政側からも早期の名義整理が求められる場面も増えています。共有不動産は、放っておくことで「資産」から「負担」へと変わってしまうのです。
共有のままにしておくリスク
不動産を共有名義のままにしておくことには、多くの法的・実務的リスクが存在します。代表的なのは、共有者全員の同意がなければ売却できないことです。これは、不動産の資産価値を活かすうえで大きな障害になります。
また、修繕や管理費、固定資産税の支払い義務も共有者で分担する必要があるため、1人が負担を拒否すれば全体が機能不全に陥ります。さらに、共有者の1人が行方不明で連絡が取れない場合、名義整理のためには家庭裁判所での手続きが必要となるなど、非常に煩雑な流れが待ち受けています。
時間が経過すればするほど、共有不動産の処理は困難になります。相続直後に何もせず先送りにすることで、次世代へと問題を繰り越してしまうことになるのです。
菱田司法書士法人では、こうした事態を防ぐため、相続後すぐの段階での名義整理・登記変更・共有解消の提案を行っています。「共有」の状態を理解し、早期に手を打つことが、資産を守る最大の対策となります。
不動産共有における典型的な相続トラブル

意見がまとまらず活用できない現実
共有名義の不動産は、原則として共有者全員の合意がなければ活用できません。そのため、相続後に誰かが「売りたい」、他の誰かが「住み続けたい」と考えた場合、意見の対立によって一切の手続きが進まないという状況に陥ります。
実際、家族内で意見が合わず、不動産をどうすることもできないまま何年も経過してしまうケースは非常に多く見られます。住み手もおらず、売却もできない状態では、不動産の価値は徐々に失われていく一方です。
こうした事態は、相続人それぞれの立場が違うからこそ起きやすく、たとえば「同居していた者」と「遠方に住む者」では温度差も大きくなりがちです。相続をきっかけに、共有という制度の非効率性に直面することは決して珍しくありません。
修繕費や税金の分担トラブル
相続により複数人で所有することになった不動産では、固定資産税や修繕費などの費用も共有者全員で分担する必要があります。しかし、実際には「支払う人」と「支払わない人」が出てくることが多く、公平な管理が困難になるのが現実です。
たとえば、長男が実家を管理しているにもかかわらず、次男や三男が費用負担に協力しない場合、長男だけが経済的負担を背負うことになり、不満やトラブルの原因になります。
また、費用の支払いだけでなく、名義が共有のままではリフォームや解体なども全員の同意が必要となるため、ちょっとした修繕でさえ実行できなくなることもあります。
このように、共有状態の不動産は相続人全員の責任が問われるにもかかわらず、実務上は誰か1人に大きな負担が集中しやすいという構造的な問題を抱えています。
相続人の一部が連絡不通なケース
不動産を共有している相続人の中に、長年音信不通の兄弟姉妹や、海外に移住したまま連絡が取れない人が含まれている場合、共有名義の整理は一気に困難になります。
名義の変更や売却などの手続きには、原則として全共有者の同意が必要です。つまり、1人でも所在が不明であると、不動産全体の活用や処分ができなくなるのです。
このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てたり、「失踪宣告」などの手続きを行う必要があり、相続手続きが非常に煩雑で長期化してしまうことも少なくありません。
共有のままにしておくことは、今後連絡が取れなくなる可能性のある相続人がいる場合、リスクがさらに高くなるということを意味します。早い段階で共有解消を進めることが、最善のリスク管理です。
家族関係の悪化と長期化する問題
不動産の共有は、法律上の問題であると同時に、感情的な対立を引き起こしやすいテーマでもあります。相続によって共有となった土地や建物をどう扱うかをめぐって、これまで良好だった家族関係が壊れてしまうことも珍しくありません。
たとえば、「自分は介護に尽力したのに、相続分が平等なのは納得できない」といった不満や、「費用を負担しているのに、他の相続人が無関心」という不公平感が、家族間のわだかまりを増幅させます。
さらに、このような問題を放置すると、次の相続が発生し、名義人が孫世代まで増えてしまうことで、話し合い自体が成立しなくなる事態も起こります。
菱田司法書士法人では、「今ならまだ間に合う」段階での解決に力を入れています。法律的手続きを行いながらも、感情的な対立を避けるための対話支援や合意形成のサポートも重視しています。
相続前からの対策がなぜ必要か
不動産の共有による問題の多くは、相続発生後に一気に顕在化します。そのため、相続が発生してから対策を考えるのでは遅いケースも多く、本来は生前の段階から準備しておくべき内容だといえます。
たとえば、遺言書の作成によって、特定の相続人に不動産を単独で相続させることや、代償分割を用いて現金と引き換えに不動産を渡す形を明示しておくことで、共有名義の回避が可能となります。
また、家族信託や贈与の制度を活用することで、相続時の共有リスクを回避するスキームも構築できます。これらは法律知識と実務の両方を必要とするため、司法書士などの専門家と事前に相談しておくことが不可欠です。
「うちはまだ大丈夫」ではなく、「今のうちに動くべきかもしれない」と考えることが、将来の相続トラブルを未然に防ぐ第一歩となります。共有は、回避できるリスクです。
共有名義を解消する方法

単独名義への持分買取と代償分割
不動産の共有状態を解消する最も基本的な方法は、誰か1人が他の共有者の持分を買い取って単独名義にすることです。これを「持分買取」と呼びます。たとえば、兄弟3人で共有していた土地を、長男が次男・三男から持分を買い取れば、不動産は長男の単独所有になります。
この際、現金で持分相当額を支払うのが「代償分割」という手法です。相続時の遺産分割協議の中でこの方法を選択すれば、共有を避けつつ、それぞれが納得できる形に整えることが可能です。
ただし、代償金を用意する側には一定の資金力が必要であり、相続財産のバランス調整や税務面の配慮も求められます。菱田司法書士法人(東京都大田区)では、司法書士と連携する税理士の協力のもと、代償分割の提案・実行を円滑に進めるサポートを行っています。
換価分割(売却による現金分配)
不動産を共有したままにするのではなく、売却して現金に換え、それを相続人で分ける方法が「換価分割」です。これは、使い道が決まっていない共有不動産や、相続人間で居住希望がない場合に非常に有効な選択肢です。
この方法では、不動産を一旦第三者に売却し、その売却代金を持分割合に応じて配分します。売却によって名義整理と資産分割が同時に行えるため、実務的にもスムーズです。
ただし、注意点として、売却には全共有者の合意が必要であり、誰か1人でも反対すれば進めることができません。また、売却による譲渡所得税が発生する可能性もあるため、事前に税務上の確認も不可欠です。
菱田司法書士法人では、換価分割を前提とした売却支援、不動産会社との連携、登記処理まで一貫して対応可能です。実際に東京都大田区内でも多くの事例に関与しており、ご安心いただける体制を整えています。
現物分割のメリットと限界
共有状態を解消する手段の一つに、現物分割という方法があります。これは、土地などの不動産を実際に分けて、それぞれを単独名義で所有する方法です。たとえば、敷地を2筆に分けて兄弟で1区画ずつ所有するといった形です。
この方法のメリットは、不動産を売却せずに相続人がそれぞれ実物として保有できる点にあります。家族の誰かが住み続けたいという希望がある場合には、現物分割がうまく機能するケースもあります。
ただし、土地の形状や建築基準法上の制約などによって、現物分割ができないケースも多くあります。また、マンションや1棟建物の場合、構造上分割が不可能なため、この手法は使えません。
そのため、現物分割は限られた条件下でのみ有効であり、専門家の判断を仰ぎながら慎重に検討することが求められます。
裁判での共有物分割請求とは
相続人同士での合意が得られない場合の最終手段として、家庭裁判所に「共有物分割請求」を申し立てる方法があります。これは、共有状態を裁判所の判断で強制的に解消する法的手段です。
この制度を利用すると、現物分割・代償分割・換価分割のいずれかが裁判所の判断によって実施されることになります。ただし、実際には不動産の競売による売却(換価)が選択されることが多く、市場価格よりも安く処分されてしまうリスクがあります。
さらに、家庭裁判所での審理には時間と費用がかかり、相続人同士の感情的な対立を深めてしまう結果にもなりかねません。
菱田司法書士法人では、裁判に発展する前の段階での合意形成支援を重視しています。どうしても調整が難しい場合には、提携弁護士と連携して、必要な法的手続きを適切に進行させる体制も整えています。
家族会議と合意形成の進め方
共有名義の問題を解消するうえで、もっとも大切なのは相続人全員による「合意形成」です。そのためには、家族間での率直な話し合い=家族会議を設けることが極めて重要です。
不動産の将来的な利用、誰が住むのか、売却の希望、費用負担のあり方など、具体的な内容を明らかにすることで、トラブルの回避につながります。特に高齢の相続人がいる場合や、遠方在住の相続人がいる場合には、早い段階での意志確認が不可欠です。
菱田司法書士法人では、第三者として公平な立場から家族会議の進行をサポートすることも可能です。単なる法手続きだけではなく、相続人同士の意見をすり合わせ、円満な解決を目指すためのコンサルティングも行っております。
不動産の共有は、話し合いのタイミングと姿勢次第でスムーズに解消できる可能性があります。先送りせず、今こそ一歩を踏み出していただきたいと考えています。
共有を回避するための事前対策
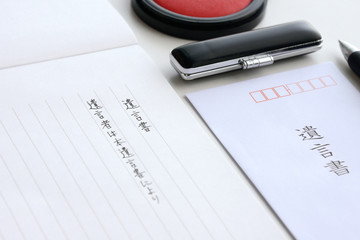
遺言書による単独相続の指定
相続時に不動産を共有名義にせず、単独で相続させるための最も有効な方法が「遺言書」の作成です。遺言書によって、誰にどの不動産を相続させるのかを明示しておけば、法定相続分による自動的な共有状態を回避することができます。
たとえば、「長男に自宅を相続させ、他の相続人には預金を分配する」といった内容を遺言に残すことで、不動産の名義を1人に集約することが可能になります。このような代償分割の意思表示がなされていれば、トラブルなく相続手続きが進みやすくなります。
ただし、遺言書には法的な形式や記載方法のルールがあり、不備があると無効になる恐れもあります。菱田司法書士法人では、公正証書遺言の作成支援を通じて、法的に確実な相続対策をサポートしています。
家族信託でスムーズな承継を実現
近年注目されているのが、「家族信託」という仕組みを使った不動産の承継方法です。これは、親が元気なうちに信頼できる家族に不動産の管理を任せ、将来的に特定の相続人に名義を引き継がせる契約です。
たとえば、「親が亡くなったら長男に土地を相続させる」という信託契約を結んでおけば、共有状態を経ることなく、スムーズに単独名義へと移行できます。この方法は、遺言とは異なり、生前の管理・運用にも活用できる点が大きなメリットです。
また、認知症対策にもなるため、高齢の方にとっては安心して不動産管理を託せる手段となります。菱田司法書士法人では、東京都大田区を中心に、家族信託に関する実績も豊富で、柔軟な設計をご提案しています。
贈与との併用による名義整理
生前に不動産の名義を整理しておきたい場合には、「贈与」も有効な手段です。特に、相続が発生する前に、不動産を希望する相続人へ贈与しておけば、相続時に共有状態になることを防げます。
たとえば、長男が将来的に実家を引き継ぐ意思がある場合、親の存命中に名義変更を行い、他の相続人には金融資産などで調整する形を取れば、後のトラブルを回避しやすくなります。
ただし、贈与には贈与税や登録免許税、不動産取得税などの課税が発生するため、贈与の時期や方法について慎重な判断が必要です。税務的な観点も含めて検討するには、司法書士と税理士の連携が不可欠です。
当法人では、相続・不動産・税務の三位一体での支援体制を構築し、ご家族にとって最適なタイミングと手法をアドバイスしています。
高齢の親名義の不動産の注意点
親の名義である不動産が将来相続の対象となる場合には、早めにその整理方法を検討しておくことが非常に重要です。なぜなら、親が高齢で判断能力が低下してからでは、名義変更の手続きができなくなる可能性があるからです。
認知症が進行すると、不動産の売却や贈与はもちろん、遺言書の作成も困難になります。結果として、相続が発生した後に不動産が共有名義となり、手続きが複雑化するリスクが高まります。
このような場合、任意後見制度や家族信託などを活用することで、親が判断能力を保っているうちに、スムーズな管理と承継の準備を整えることが可能です。
「まだ元気だから大丈夫」ではなく、「今が最後のチャンスかもしれない」という意識での早期対策が、将来の共有トラブルを未然に防ぎます。
専門家による総合的な事前設計
不動産の相続をめぐる問題は、単に登記をすれば済むような話ではなく、法務・税務・感情面が複雑に絡み合う分野です。そのため、事前対策を行う際には、経験豊富な専門家のサポートが不可欠です。
司法書士は登記手続きの専門家ですが、それだけでなく、相続人全体の状況を把握し、法的に適切かつ実務的な形で不動産の承継方法を提案できる立場にあります。さらに、必要に応じて弁護士や税理士とも連携しながら、ワンストップで支援を提供できます。
菱田司法書士法人(東京都大田区)では、相続に強い司法書士として、遺言・信託・贈与などあらゆる選択肢を比較しながら、最適な解決策をご提案しております。
「うちのケースではどうすればいい?」という段階でも、ぜひ一度ご相談ください。共有を回避するための設計は、時間的余裕がある今こそが最適なタイミングです。
菱田司法書士法人の共有不動産サポート

地域密着90年の実績と信頼
菱田司法書士法人は、1933年に創業し、終戦の年に東京都大田区へ移転してから90年以上にわたり、地域の皆さまの相続と不動産に関する手続きを支援してきました。私たちは、共有名義によるトラブルを含む複雑な案件に多数対応してきた経験があります。
長年にわたる信頼と実績により、「まず菱田さんに相談してみよう」と多くのお客様にお選びいただいています。相続で発生する共有名義の課題は、誰にでも起こり得る身近な問題であり、それを安心して相談できる存在であることが、当法人の誇りです。
地域の実情に詳しいからこそ、東京都大田区特有の不動産事情にも柔軟に対応できることが、私たちの強みです。
ワンストップでの相続支援体制
不動産の共有問題を含む相続では、司法書士だけでなく、税理士、弁護士、不動産会社などの専門家と連携する必要が出てくるケースも少なくありません。手続きや相談先が多岐にわたると、相続人の負担が大きくなってしまいます。
そこで、菱田司法書士法人では、必要なすべての手続きを「ワンストップ」で対応できる体制を整えています。登記業務はもちろん、税務申告や紛争対応、不動産売却の仲介調整まで、窓口を一本化し、安心と効率を提供いたします。
共有名義の解消や遺産分割の設計など、複雑な課題を抱えていても、当法人が中心となって手続きを統括することで、スムーズな相続の実現が可能です。
ご相談から手続き完了までの流れ
菱田司法書士法人では、初回のご相談から手続き完了までを明確なステップでご案内しています。不動産の相続に関して、「何から始めていいかわからない」という方にも、安心してご相談いただける仕組みをご用意しております。
おおまかな流れは以下のとおりです:
- ご予約(電話・メール・オンライン)
- 初回相談(無料)で状況ヒアリング
- 不動産調査・戸籍収集・財産確認
- 遺産分割協議・共有整理プランのご提案
- 各種登記手続きの実行・完了書類のお渡し
特に共有名義の不動産では、持分調整や代償分割などの判断が必要な場合も多いため、ひとつひとつの手続きに丁寧に対応しています。
高齢者・遠方対応も柔軟に実施
相続に関するご相談の中には、「親が高齢で外出が難しい」「共有者が地方や海外にいて話が進まない」といったお悩みも多く寄せられます。
菱田司法書士法人では、高齢の方への訪問相談や、遠方の相続人とのオンライン面談、郵送での手続き対応など、多様なケースに応じた柔軟な対応を行っております。
また、共有名義の解消を目指すうえで、遠方の相続人の意思確認や書類取得が必要な場合にも、私たちが窓口となりスムーズに取りまとめます。
「家族がバラバラに住んでいるから難しいかも…」と諦めず、まずは私たちにご相談ください。どのような環境でも解決策は必ず見つかります。
不動産共有整理で得られる安心
不動産が共有状態のままであることは、相続人にとって常に「不安定な所有関係」に晒されているということです。この状態を整理し、単独所有または適切な分割を行うことで、「財産を守る」「活用する」「次世代へつなげる」ことが初めて可能になります。
菱田司法書士法人が目指すのは、単なる書類手続きの代行ではありません。お客様一人ひとりのご事情を丁寧に伺い、「心の負担」も軽減することです。
相続した不動産を安心して引き継ぐために、そして共有という複雑な問題から解放されるために、私たちの専門知識と経験を活かしていただければ幸いです。
よくあるご質問(Q&A)

Q1. 相続した不動産が共有名義になっています。売却するにはどうすればいいですか?
A. 不動産が共有の場合、共有者全員の同意がないと売却はできません。そのため、事前に話し合いを行い、合意形成が必要です。共有名義を解消して単独名義にする方法もありますので、まずは状況を整理し、司法書士にご相談ください。
Q2. 相続が発生しましたが、名義変更の登記をしていません。共有状態でも問題ないですか?
A. 登記をせずに放置しておくと、後々さらに複雑な相続が発生し、共有者が増えていくリスクがあります。2024年からは相続登記が義務化され、罰則の対象になる可能性もあるため、早めに手続きすることが重要です。
Q3. 親の名義のままになっている不動産があります。今からでも整理できますか?
A. はい、可能です。相続人を調査し、遺産分割協議を行ったうえで、共有名義を避けた形での登記変更も可能です。放置期間が長い場合でも、菱田司法書士法人がしっかりサポートいたします。
Q4. 兄弟で不動産を共有していますが、ひとりが修繕費を払ってくれません。どうすればいいですか?
A. 共有者は持分に応じた義務がありますが、強制的に支払わせるには法的手続きが必要です。まずは話し合いの余地があるかを確認し、それが難しければ共有解消の方向へ進めることも検討しましょう。
Q5. 相続人のひとりが音信不通です。不動産の共有名義はどうなりますか?
A. 所在が不明な共有者がいる場合、そのままでは登記や売却ができません。不在者財産管理人の選任など法的な対応が必要ですので、早めに司法書士に相談することをおすすめします。
Q6. 共有不動産を現金で分けたいのですが、どう進めれば良いですか?
A. 「換価分割」といって、不動産を売却して現金を分配する方法があります。共有者全員の同意が前提となりますので、話し合いのサポートや不動産会社との連携を、菱田司法書士法人が一括で支援します。
Q7. まだ相続は発生していませんが、将来の共有を避けるには何をしておけば良いですか?
A. 遺言書の作成や家族信託、生前贈与などで共有の発生を防ぐことが可能です。どの方法が最適かは家庭ごとの事情によりますので、事前に専門家へご相談ください。
まとめ

相続で不動産を受け継ぐことは、ご家族にとって大きな転機となりますが、共有名義のまま放置しておくことは多くのリスクを伴います。使えない、売れない、意見が合わない——こうしたトラブルは、すべて共有状態から生じると言っても過言ではありません。
共有の整理は、不動産を資産として守り、将来の安心につなげるために欠かせないステップです。相続発生後の対応はもちろん、生前の段階から備えることによって、家族間のトラブルや手続きの煩雑さを避けることも可能になります。
私たち菱田司法書士法人(東京都大田区)は、90年以上にわたり、地域の皆さまの相続・不動産に関する問題に向き合ってきました。登記の手続きから共有名義の整理、各専門家との連携まで、ワンストップで確実かつ丁寧に対応いたします。
「何から始めていいかわからない」そんなときこそ、まずはご相談ください。不安や疑問をひとつずつ解消しながら、ご家族にとって最善の形を一緒に考えてまいります。相続も、不動産も、共有のことも——ぜひ、菱田司法書士法人にお任せください。