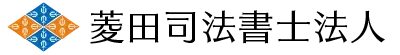ブログ
相続で不動産が共同名義に?放置リスクと対策を解説|菱田司法書士法人(東京都大田区)

相続において不動産をどう扱うかは、多くのご家庭で避けて通れない課題です。特に、相続人が複数いる場合、土地や建物が共同名義になることが一般的であり、これが後々のトラブルの原因になることも少なくありません。
共同名義の不動産は、売却・利用・修繕などあらゆる場面で相続人全員の合意が必要となるため、ちょっとした意見の違いでも手続きが進まない事態に陥ってしまいます。こうした問題を未然に防ぎ、スムーズな相続を行うためには、正確な知識と適切な対策が求められます。
東京都大田区にある菱田司法書士法人は、90年以上にわたり、地域の皆さまの相続に関する悩みに寄り添い、丁寧な支援を行ってきました。不動産が絡む相続や、共同名義の整理に関しても、豊富な経験を活かして問題の本質に対応します。
本記事では、「相続」手続きにおける「不動産」の扱い方や、「共同名義」によるリスクと対処法について、わかりやすく解説していきます。「何から始めたらいいかわからない」とお悩みの方も、まずはこの記事を通じて一歩踏み出すヒントを見つけてください。
相続不動産が共同名義になる仕組み

共同名義とは何か
共同名義とは、ひとつの不動産に複数人の名義人が存在する状態を指します。たとえば、相続により兄弟3人で親の土地を受け継いだ場合、それぞれが3分の1ずつの持分を持つことになり、これが共同名義の典型的な形です。相続によって発生する共同名義は、一見公平に見えますが、実際には大きな管理・運用上の課題を抱えることが多いのです。
相続の場面では、不動産を法定相続分に応じて分けることがよくありますが、その結果として不動産が複数人の共有財産となるケースが圧倒的に多くなります。つまり、「不動産は分けられないが、権利は分けられる」という理屈に基づいて、共同名義が成立するのです。
しかし共有者全員の同意がなければ不動産の処分や変更ができないため、共同名義は相続後のトラブルの温床にもなります。名義人の1人でも反対すれば売却できない、あるいは遠方に住んでいて手続きが進まないといったケースが実際に起きています。
このように、相続によって共同名義の不動産が生まれる仕組みは、単に権利の公平性を保つための方法であり、必ずしも相続人全体にとって使いやすい形とは限らないのが実情です。
相続時に共同名義になるケース
不動産が相続される際、遺言書が存在しない、もしくは明確な分割方法が決められていない場合には、相続人全員での共有とするのが一般的です。これが、共同名義になる最も多いケースです。
特に東京都大田区のように、不動産価値が高く土地の分筆が難しいエリアでは、共同名義での登記が選択されやすい傾向にあります。たとえば、築年数の経った一戸建てや、賃貸併用住宅などでは、それぞれの相続人が一部を単独で所有するという方法が難しく、やむを得ず共有登記がなされるのです。
また、仲の良い兄弟姉妹間で「とりあえず共有にしておこう」と判断するケースも見られますが、この“とりあえず”が後の問題に繋がることが多いのです。なぜなら、不動産の名義は一度共同にしてしまうと、あとからの単独名義への変更には手間も費用もかかるからです。
つまり、共同名義は「相続手続きの便宜上」選ばれることが多いが、長期的には不都合が生じる可能性が高いという現実を知っておく必要があります。
相続登記を放置するとどうなるか
相続によって取得した不動産の名義変更(相続登記)をしないまま放置すると、共同名義どころか「名義不明不動産」という深刻な社会問題に発展するリスクがあります。相続人の一部が亡くなり、さらにその相続が発生することで、権利者が枝分かれし、複雑な状態になるからです。
登記を怠ると、不動産の利用や売却ができない状態になり、空き家問題の原因にもなります。東京都大田区でも、老朽化した家屋がそのままになっている背景には、相続登記がなされていない共同名義不動産の存在が関係しているケースが多く見られます。
さらに、2024年4月の法改正により、相続登記は義務化され、3年以内に行わなければ過料(10万円以下)の対象となるようになりました。つまり、放置すること自体が法的リスクとなるのです。
「何代にもわたる共同名義」状態を避けるためにも、早期の相続登記と名義整理は非常に重要です。菱田司法書士法人では、こうした複雑なケースも多数解決に導いてきました。
相続人のトラブルの実例
共同名義の不動産を巡る相続トラブルは、実際に多くのご家庭で起きており、決して他人事ではありません。たとえば、あるご兄弟が相続した実家を「将来的に誰かが住むまで保有しておこう」と共有状態で放置していたところ、数年後に一方が売却を希望し、もう一方が反対。話し合いがまとまらず、家庭裁判所での共有物分割請求にまで発展した例があります。
また、一方が不動産の固定資産税や修繕費を支払い続け、もう一方が何もしないという不公平感から、関係性が悪化してしまうケースもあります。このような状況は、「最初にしっかり話し合っておけば防げた」問題であることがほとんどです。
特に、高齢の相続人が遠方に住んでいる場合や、連絡が取りにくい相続人がいる場合は、共同名義にしてしまうと今後の処理が非常に難しくなります。
こうした実例からも、相続の初期段階で専門家に相談し、共同名義の可否を慎重に判断することが重要であることがわかります。
共同名義を避ける方法はあるのか
相続において不動産を共同名義にしない方法として、最も有効なのが遺言書や遺産分割協議によって単独名義にすることです。たとえば、「長男に土地をすべて相続させ、代償として他の兄弟に預貯金を渡す」といった代償分割を行えば、単独名義での相続が可能になります。
また、相続開始前に生前贈与や家族信託を活用しておくことで、共同名義を回避できる場合もあります。たとえば、元気なうちに自宅の名義を長男に移しておき、その代わりに生活資金などを公平に分配するといった形です。
遺産分割協議においても、「とりあえず共有」は避け、しっかりと将来の管理・処分の方針を決めておくことが大切です。共同名義は、平等に見えて実はトラブルの種。だからこそ、名義を一本化する方向で話し合いを進めることが望まれます。
菱田司法書士法人では、不動産の名義整理を見越した相続設計をサポートしています。相続対策を「相続が起きる前」に講じることが、結果として相続人全員の負担を軽くするのです。
不動産を共同名義で相続した場合のリスク

売却が困難になる理由
相続した不動産が共同名義である場合、売却にはすべての共有者の合意が必要となります。つまり、相続人のうち一人でも反対すれば、不動産の売却は不可能となり、財産を現金化して分配したいと考えている人にとっては大きな障害です。
また、共有者が高齢で意思確認ができなかったり、音信不通になっていたりすると、売却手続き自体がストップしてしまいます。これは、東京都大田区のように不動産価格が高く、需要がある地域ほど大きな損失につながりかねません。
「売れるはずの不動産が売れない」という状況は、相続人にとって精神的にも経済的にも負担が大きく、次の世代にも未処理の問題を引き継いでしまう恐れがあります。共同名義にすることで不動産の資産価値を活かせなくなることがあるというリスクを理解しておくことが大切です。
修繕や税金負担の問題
共同名義の不動産では、固定資産税や修繕費を誰がどのように支払うかという問題が発生します。名義上は共有でも、実際の支払いや管理を一部の相続人が担う場合、不公平感が生じてトラブルの原因となるのです。
たとえば、兄弟で共同相続した住宅に片方だけが居住し、もう一方は別の場所で暮らしているケースでは、「住んでいるならそちらが負担すべき」といった感情的な対立が生まれることがあります。さらに、税務上は共有持分に応じた納税義務があるため、支払わない名義人がいれば、ほかの共有者が督促を受けることもあります。
不動産の共同名義は、維持コストや責任の所在を曖昧にしやすく、結果として相続人全体にとって負担を増やす構造になりがちです。菱田司法書士法人では、こうした費用分担問題も含めたアドバイスを行っております。
意見の不一致による膠着状態
共同名義の最大のリスクは、意思決定の難しさにあります。不動産に関する重要な手続き――たとえば売却、賃貸、建て替え、解体などは、原則として全共有者の同意が必要です。
相続人同士が仲の良い関係であっても、価値観やライフスタイルの違いから意見が分かれることは珍しくありません。特に、それぞれの生活が異なる地域・状況にあると、物理的にも話し合いの場が持てないことが多いのです。
このようにして、「話がまとまらない」「誰かが反対している」という理由で、相続した不動産の活用が進まないまま数年が経過してしまう事例が数多くあります。これは不動産だけでなく、家族関係にも深い溝を残すリスクがあります。
法定相続分と実態のズレ
相続では法定相続分に基づいて不動産を共有するケースが多いものの、実際にその不動産を利用・管理している人とのバランスが合わないことが多くあります。たとえば、長男が親の介護をしていたにもかかわらず、相続分は他の兄弟と同等であるというケースです。
このような状況では、「自分ばかりが損をしている」と感じた相続人が不満を抱え、共同名義のままでは問題が解決できない状態に陥ってしまいます。また、利用実態に見合わない税負担をしている人が、後から名義変更を求めるトラブルも少なくありません。
相続によってできあがる共同名義は、法的には公平でも、現実には不公平感を生みやすい構造であるということを知っておくことが重要です。だからこそ、相続時には冷静かつ慎重な判断が求められます。
「共有物分割請求」の現実とは
共同名義を解消したいときに用いられるのが「共有物分割請求」という法的手段ですが、これは家庭裁判所に申し立てをして、最終的には裁判所の判断によって不動産を分割・売却するという方法です。
一見すると便利な制度に思えますが、実際には時間も費用もかかり、相続人同士の対立をさらに深めるリスクがあります。また、判決の内容によっては、自分の希望する分け方とは異なる結果になることも珍しくありません。
たとえば、不動産を競売にかける形で換価分割されてしまうと、本来の市場価格よりも安く売却される可能性が高く、損失が出ることもあります。さらに、裁判の過程で家族の関係が完全に断絶してしまうケースもあり、精神的ダメージも大きいのが実情です。
菱田司法書士法人では、共有物分割請求に至る前の段階での合意形成支援に力を入れています。無用な争いを避けるためにも、できるだけ早い段階で専門家に相談することが、最良の道です。
不動産の共有解消の方法

持分買取と代償分割の活用
相続で共同名義になった不動産を解消する方法として最も現実的なのが、持分の買取や代償分割の手法です。たとえば、兄弟姉妹のうち誰か1人が不動産を単独で相続し、他の相続人に対して相応の現金(代償金)を支払うことで、名義を一本化することができます。
この方法は、相続人間の合意があれば比較的スムーズに手続きできるうえ、不動産の価値を維持しながら名義問題を解決できるというメリットがあります。菱田司法書士法人では、不動産の評価や代償金の算定に必要な資料の収集・調整も一括して支援しています。
また、代償分割は不動産そのものを売却せずに相続問題を解決できるため、「思い出の詰まった家を手放したくない」という方にも適した選択肢です。ただし、持分買取に必要な資金をどう用意するかといった課題もあるため、相続の専門家と早い段階で相談することが大切です。
現物分割とその限界
不動産の共有解消には、「現物分割」と呼ばれる方法もあります。これは、ひとつの土地や建物を実際に分けて、各相続人が単独名義で一部を所有するという形です。
たとえば、広い土地を複数に分筆して、それぞれが登記をするケースなどがこれにあたります。しかし現実には、土地の形状や建築基準法の規制などから現物分割が難しい不動産が多く、実行可能なケースは限られます。
また、建物の場合は区分所有という制度が必要になりますが、一戸建てなどではそれ自体が困難なため、現物分割では対応しきれないこともあります。東京都大田区のように、地価の高い住宅街では土地の分筆が行政的に認められないケースもあり、現物分割だけに依存するのは現実的ではありません。
このため、現物分割は可能性としては検討すべきですが、他の方法と組み合わせて考えるべき手段であるという点を押さえておく必要があります。
換価分割の進め方と注意点
換価分割とは、共同名義の不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分け合う方法です。もっともシンプルで明快な解決方法ではありますが、前提として共有者全員の売却同意が必要となります。
たとえば、4人の兄弟姉妹で共有している不動産を売る場合、1人でも反対すれば取引が成立しません。この同意形成が困難な場合には、時間だけが経過してしまう恐れがあります。
また、売却によって得た代金に課税が発生する可能性もあるため、税務的なアドバイスも欠かせません。菱田司法書士法人では、提携する税理士との連携によって、相続後の売却に伴う税務リスクを事前に説明し、円滑な換価分割を支援しています。
不動産市場の動向も踏まえて、「今が売り時なのかどうか」を含めた総合的な判断が必要ですので、単に売却するだけではなく、慎重な判断が求められる方法でもあります。
裁判による共有物分割請求とは
すでに任意での解消が困難な場合、家庭裁判所に共有物分割請求を申し立てるという方法もあります。これは、共有者の一人が他の共有者との合意形成ができなかった場合に、裁判所の判断によって共有状態を解消するという手段です。
しかしながら、この方法は費用も時間もかかり、裁判の結果によっては不本意な形で不動産を失うことにもなりかねません。たとえば、競売による分割となると、市場価格よりも大幅に安く売却されてしまうことが多く、相続人全員が損をしてしまうケースが散見されます。
また、家族内の関係が深刻に悪化するリスクもあるため、あくまで最終手段と考えるべきです。菱田司法書士法人では、裁判に頼らず、話し合いによる円満な解決を第一に提案しております。
相続前の生前対策の重要性
不動産の共同名義問題は、相続が発生してからでは遅い場合があります。だからこそ、「相続前の生前対策」が非常に重要です。たとえば、生前に遺言書を作成し、誰にどの不動産を相続させるかを明示しておけば、共有の発生を回避することができます。
また、家族信託や任意後見制度の活用により、不動産の管理や名義変更を柔軟に行うことが可能となります。特に高齢の親が自宅を所有している場合、その不動産をどのように引き継ぐかを早い段階から考えておくことが、後のトラブル回避に繋がります。
菱田司法書士法人では、東京都大田区で多くのご家庭の生前対策を支援してきた実績があり、法律面だけでなく、ご家族の感情にも配慮した柔軟な提案を行っています。
「相続はまだ先の話」と思っている今こそ、最も対策を立てやすいタイミングです。相続人同士が揉める前に、冷静な話し合いと専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
相続不動産の共同名義を防ぐ対策

遺言書の有効な活用法
相続で不動産が共同名義になってしまう主な理由の一つが、遺言書が存在しないことです。つまり、遺言書さえあれば、不動産の相続方法を明確に指示でき、共同名義を回避することが可能になります。
たとえば、「長男に不動産を相続させ、次男・三男には金融資産を分ける」といった偏在的な配分も、遺言書であれば合法的かつ確実に実現できます。遺言書がない場合には、法定相続分に応じて共有状態になるのが一般的です。
注意点としては、自筆証書遺言の不備や紛失によるトラブルを防ぐため、公正証書遺言を選択することが望ましい点です。菱田司法書士法人では、遺言内容の法的チェックや作成サポートを行っており、相続後の不動産トラブルを未然に防ぐ体制を整えています。
不動産の単独相続を希望される方は、遺言書の作成を第一の対策として検討すべきです。
家族信託の活用例
近年注目されているのが、家族信託を利用した相続不動産の管理と承継対策です。これは、所有者が信頼できる家族に不動産の管理を託し、将来的に誰が相続するのかを契約で定めておく仕組みです。
たとえば、親が生前に「自宅を息子に相続させたいが、まだ自分が住んでいたい」という希望がある場合、家族信託を活用することで、親が住み続けながら、相続発生後に自動的に単独名義に移行させることが可能です。
これは、相続発生後に共有状態を避け、確実に不動産の所有権を一本化できるメリットがあり、東京都大田区でも高齢者の不動産対策として多く導入されています。
菱田司法書士法人では、信託契約の作成から登記手続きまで一貫して対応しており、ご家族ごとの事情に合わせた柔軟な信託設計を行っています。
事前の家族会議のすすめ
法的な手続きだけでなく、事前に家族で話し合うことこそが、最も効果的な対策です。不動産を相続した後に共有で揉める原因は、「誰が何を希望していたのか」「介護や支出のバランス」などが事前に共有されていなかったためです。
相続はデリケートな話題ですが、早い段階で「不動産を誰が引き継ぐのか」「他の相続人にどう配慮するか」を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
菱田司法書士法人では、家族会議の進め方や議題の整理、感情的対立が起こらないための第三者的支援も行っています。相続人全員が納得できる形を目指すなら、対話と法的整備の両輪が不可欠です。
贈与との併用でトラブル回避
不動産の相続を見据えて、生前贈与を活用する方法も有効な対策です。たとえば、親が存命中に特定の相続人へ不動産を贈与し、他の相続人には現金や有価証券などを贈与することで、将来的な共同名義の発生を防ぐことができます。
ただし、贈与税や不動産取得税、登録免許税などの課税関係を踏まえる必要があり、贈与が得策かどうかは総合的な判断が必要です。特に、不動産価値の高い東京都大田区の物件では、贈与時の税負担が大きくなることもあるため注意が必要です。
このような場面でも、菱田司法書士法人では税理士と連携し、税コストも考慮した贈与・相続プランをご提案しています。贈与は相続と組み合わせることで、リスクを最小限に抑えることができる有効な手段です。
専門家による対策支援の必要性
不動産の相続問題は一見単純に思えても、登記、税務、民法、家族関係など複数の要素が絡み合う複雑な問題です。そのため、自己判断で手続きを進めてしまうと、結果的に共同名義の状態を招き、後々大きなトラブルを抱えることにもなりかねません。
だからこそ、早い段階で専門家の支援を受けることが極めて重要です。菱田司法書士法人では、東京都大田区を拠点に、地域に根差した視点と法務のプロフェッショナルとしての知識を融合させ、お客様一人ひとりに合った相続不動産対策を提供しています。
また、弁護士・税理士・不動産会社などと連携した「ワンストップ支援体制」を確立しており、どのようなご相談にも迅速・丁寧に対応いたします。
相続・不動産・共同名義に関するお悩みは、早めにプロへご相談ください。それが、将来の安心へとつながります。
菱田司法書士法人によるサポートの強み

東京都大田区で90年以上の実績
菱田司法書士法人は、昭和8年に品川区で創業し、昭和20年に現在の東京都大田区に移転してから90年以上にわたり地域の法務を支えてきた司法書士事務所です。長い歴史の中で、相続や不動産に関する数多くのご相談を受けてきたことが、私たちの何よりの強みです。
不動産の名義変更や相続登記に関する専門的な知識と、実務に基づいた豊富な経験を併せ持つ体制が整っており、共同名義の整理や相続の計画立案にも迅速かつ的確に対応できます。
地域の皆様から「相続のことなら、まず菱田に相談してみよう」と思っていただける存在であることが、私たちの誇りです。地元に根ざし、世代を超えて信頼されてきた歴史が、安心の証です。
他士業連携によるワンストップ対応
不動産の相続問題では、司法書士の業務だけでは完結しないことが多々あります。税務申告が必要な場合は税理士、遺産分割でもめた場合は弁護士、売却が関係する場合は不動産会社との連携が必要になることもあります。
菱田司法書士法人では、これらすべてのケースに対応できるよう、各分野の専門家との信頼関係を築いており、必要に応じてスムーズに連携を行います。そのため、お客様自身があちこちの専門家を探して手間をかける必要はありません。
複雑な相続や不動産の共同名義の問題も、当法人が窓口となり、全体を見渡しながら調整・手続きを進めることで、時間も手間も大幅に軽減されます。
ご相談から手続き完了までの流れ
菱田司法書士法人では、初回相談を丁寧にヒアリングすることからすべてが始まります。相続の背景やご家族の関係、不動産の内容、将来の希望などを詳細にお伺いし、その情報をもとに最適な解決プランをご提案します。
ご相談の流れは以下の通りです:
- 無料相談のご予約・実施(電話・オンライン対応可)
- 相続・不動産の調査、必要書類の取得
- 遺産分割協議書や遺言書の整備
- 登記や名義変更の実施
- 共有名義の整理や税務手続きも同時進行で対応
このように、相続と不動産にまつわる全体の流れを、ワンストップで完結できるのが当法人の大きな特長です。特に共同名義が関係する複雑な案件では、このような体制が大きな安心につながります。
高齢者や遠方の方への柔軟な対応
東京都大田区内だけでなく、他県に住む相続人や高齢で外出が難しい方からのご相談にも柔軟に対応しております。訪問対応や郵送・オンラインでの手続きも積極的に活用し、どなたでも安心してご相談いただける環境を整えています。
相続では、遠方に住む相続人が多く、不動産が共同名義となってしまうケースが少なくありません。このような場合でも、菱田司法書士法人では全員の意向を尊重しながら、スムーズな手続き進行を可能にしています。
「時間がない」「手続きが不安」「親が高齢なので対応が難しい」といったお悩みも、私たちにお任せください。
相談無料・初回面談で得られる安心
相続や不動産の問題は、「誰に、何を、いつ、相談すればいいのか分からない」というお声が非常に多いのが現実です。だからこそ、菱田司法書士法人では初回のご相談を無料で承っております。
「まだ何も決まっていないけど話を聞いてみたい」
「共同名義にしてしまったが今からでも整理できるのか」
「不動産が複数あるので分け方に困っている」
こうした段階でも、ぜひお気軽にご相談ください。当法人では、法律的な視点だけでなく、お客様のご家族や生活の背景にも寄り添いながらアドバイスいたします。
初回面談で得られるのは「知識」だけでなく、「安心」と「今後の道筋」です。相続不動産のことでお悩みの方は、菱田司法書士法人にぜひ一度ご相談ください。
よくあるご質問(Q&A)

Q1. 相続した不動産が共同名義になっています。売却はすぐできますか?
A. 原則として、共有者全員の同意がなければ売却できません。1人でも反対する共有者がいれば売却は不可能になります。まずは共有者同士で方針を話し合い、合意形成が難しい場合は、菱田司法書士法人が第三者として調整をお手伝いすることも可能です。
Q2. 相続登記を放置している共同名義の土地があります。今からでもできますか?
A. はい、可能です。ただし、2024年4月から相続登記は義務化されており、3年以内に行わないと10万円以下の過料の対象になります。不動産を放置すると名義が複雑化し、手続きがさらに難しくなるので、早めの対応が重要です。
Q3. 生前に対策すれば、相続で不動産が共同名義になるのを防げますか?
A. はい、遺言書や家族信託を活用することで防ぐことが可能です。特に遺言書で明確に相続先を指定すれば、不動産を単独名義で引き継がせることができます。ご家族での事前の話し合いも有効な手段です。
Q4. 遺言がない場合、共同名義になるのは避けられませんか?
A. 基本的には、遺産分割協議の結果によって名義が決まります。協議で1人に不動産を集中させることができれば、共同名義を回避することも十分可能です。話し合いが難しい場合は、司法書士によるサポートで解決が見えてくることもあります。
Q5. 共有状態の不動産をどうしても分けられない場合はどうなりますか?
A. 話し合いがまとまらない場合、「共有物分割請求」という法的手続きを使うことになります。ただし、家庭裁判所での手続きは時間も費用もかかり、関係悪化のリスクもあるため、事前の合意が望ましいです。
Q6. 相続人の1人が行方不明です。名義変更はできますか?
A. 原則として行方不明者の同意なしには名義変更はできません。ただし、不在者財産管理人を選任するなどの法的手続きによって進めることは可能です。こうした複雑な案件も、菱田司法書士法人では対応実績が豊富にあります。
Q7. 相続した不動産が東京都以外でも対応してもらえますか?
A. はい、東京都大田区を拠点としつつも、全国の不動産に関する相続手続きに対応可能です。登記は全国一律のルールに基づくため、遠方の相続不動産もご相談ください。
まとめ

相続によって不動産が共同名義になることは珍しいことではありませんが、そのままにしておくと大きな問題に発展するリスクを抱えています。売却や管理、修繕、税負担、さらには家族関係の悪化まで、多くのトラブルの温床となってしまうのです。
だからこそ、「相続」「不動産」「共同名義」それぞれの観点から冷静に状況を整理し、早めに専門家に相談することが重要です。共同名義の解消には、代償分割、家族信託、生前贈与などさまざまな方法がありますが、それらを適切に選び実行するには、法律と実務の知識が不可欠です。
東京都大田区の菱田司法書士法人では、90年以上の歴史の中で、数多くの相続・不動産問題を解決してまいりました。お客様一人ひとりに寄り添いながら、安心して次の世代へ財産をつなげていけるよう、丁寧かつ誠実なサポートを提供しています。
「相続が起きたけれど、何から始めればいいかわからない」
「不動産が共同名義になってしまって困っている」
「家族が揉めないように事前に対策をしておきたい」
このようなお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽に菱田司法書士法人へご相談ください。専門家と一緒に、一歩ずつ解決に向けて進んでいきましょう。