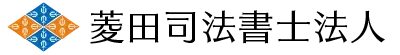ブログ
相続の相談先は司法書士?税理士?違いと役割を徹底解説|菱田司法書士法人

相続は、誰にでも関係のある身近な法律問題です。
しかし、いざ相続が発生すると「何から始めればいいのか」「どの専門家に相談すれば良いのか」と悩む方が多くいらっしゃいます。実際には、不動産や預貯金の名義変更、遺産分割協議、税金の申告など、複数の分野にわたる手続きが同時進行で求められるため、スムーズに進めるためには専門家の支援が必要不可欠です。
そうした中で注目されるのが、司法書士による法的サポートと、税理士による税務面のアドバイスです。司法書士は主に相続登記や遺産分割協議書の作成など、不動産や財産の法的な名義変更に関わります。一方、税理士は相続税の計算や申告、節税対策などを担当し、相続における税金の専門家として重要な役割を果たします。
当法人である菱田司法書士法人(東京都大田区)は、昭和8年の創業以来、数多くの相続に関するご相談を承ってきました。司法書士としての専門性はもちろん、必要に応じて経験豊富な税理士や弁護士、不動産会社などとも連携し、お客様にとって最善の相続の形を実現することを大切にしています。
この記事では、「相続」「司法書士」「税理士」の3つの視点から、それぞれの役割や対応範囲、連携の必要性を詳しく解説し、相続に関して「何を・誰に」相談すべきかが明確になることを目的としています。
相続の準備を始めたい方、すでに発生した手続きを進めたい方、「司法書士や税理士に依頼すべきか」と迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
そして、「専門家にまとめて相談したい」と感じたときは、ぜひ東京都大田区の菱田司法書士法人にお声かけください。
相続の基本と司法書士・税理士の役割

相続とは何か?
相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産や義務を、法定相続人が受け継ぐ法律行為を指します。財産には、不動産や預貯金、有価証券だけでなく、借金などの負債も含まれるため、相続人にとっては慎重な判断が求められます。
現代の日本では、高齢化や家族構成の変化に伴い、相続の形も複雑化しています。単なる「財産の引き継ぎ」ではなく、感情や関係性、今後の生活にも大きく影響するため、法律的・実務的な知識を持った専門家のサポートが不可欠です。
また、相続は放置すると法的なトラブルに発展するリスクもあります。たとえば、不動産の名義を被相続人のままにしておくと、いずれ再相続が発生した際に相続人が増え、遺産分割が困難になる可能性が高くなります。
「相続はまだ先の話」と考えがちですが、いざ発生するとすぐに期限付きの手続きが始まるのが現実です。相続放棄の期限は3か月、相続税の申告期限は10か月とされており、何も準備をしていなければ、慌てて動くことになります。
そこで注目されているのが、生前からの相続対策や専門家との連携です。東京都大田区で長年活動している「菱田司法書士法人」では、相続の入り口から出口まで、お客様の状況に応じて最適なサポートを提供しています。
司法書士の役割
司法書士は、不動産や相続財産の登記など「権利や財産に関する法的な手続き」を扱う法律の専門職です。特に相続においては、下記のような役割を担っています。
- 相続登記(不動産名義変更)の代理申請
- 遺産分割協議書の作成支援
- 戸籍の収集、相続関係説明図の作成
- 遺言書の文案作成支援と保管方法のアドバイス
相続財産に不動産が含まれている場合は、司法書士の専門知識が欠かせません。相続登記を怠ると、将来的な不動産売却や利用に支障が出るだけでなく、法改正により登記義務違反として過料の対象になる可能性があります。
また、遺言書の内容が不明確だったり、相続人が多数いたりする場合には、登記に必要な書類が複雑化することもあります。その際、法律の枠組みに基づいて正確に処理を行う司法書士のサポートが、相続人全体の安心につながります。
税理士の役割
税理士は、相続税の計算・申告・節税アドバイスを専門とする税務のプロフェッショナルです。相続税の申告が必要となるのは、課税価格が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合ですが、課税の有無に関わらず評価や申告準備は必要です。
税理士の主な業務は以下の通りです。
- 相続財産の評価(不動産、株式、事業資産など)
- 相続税の申告書作成
- 納税方法・分割納税の提案
- 生前贈与のアドバイス
相続税は、財産の種類によって評価方法が大きく異なるため、一般の方が自力で正確に申告を行うのは困難です。加えて、適切な控除や特例を活用しなければ、不要な納税が発生する可能性もあります。
特に二次相続を見越した節税対策や、将来的な相続を視野に入れたトータルプランニングにおいて、税理士の視点は不可欠です。司法書士と税理士の連携があってこそ、相続の“手続き”と“税務”が一体となり、スムーズかつ効率的な相続が実現します。
相続手続きの流れ
相続手続きは以下のように進みます。それぞれの段階で必要な専門家のサポートが異なります。
- 死亡届の提出・火葬許可
- 遺言書の有無の確認(公正証書 or 自筆証書)
- 相続人の調査(戸籍取得)
- 相続財産の調査と評価(不動産、預貯金、株式など)
- 遺産分割協議
- 相続登記、預金解約、名義変更
- 相続税の申告と納付
司法書士は主に2~6にかかわる手続き全般を支援し、税理士は4~7の財産評価・税務計算・申告書提出までを担います。円滑に手続きを進めるためには、これらのプロセスを理解したうえで、早めに両者と連携することが望ましいです。
相続における注意点
相続では以下のような点に特に注意が必要です。
- 相続放棄は原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。期限を過ぎると借金などの負債も含めて全てを引き継ぐことになります。
- 相続税の申告は10か月以内ですが、納税資金の確保や物納・延納の準備も含めると、さらに早期対応が必要です。
- 遺言書が複数存在する場合や記載内容が曖昧な場合、手続きが停止することがあります。必ず専門家に確認を。
- 相続人間でのトラブル回避のためには、中立的な第三者として司法書士が介入することが有効です。
特に近年では「空き家問題」や「名義人不明土地」など、相続を放置したことによる社会問題も顕在化しています。相続は「自分たちだけの問題」とせず、社会全体への影響も意識した行動が必要です。
菱田司法書士法人の特徴

歴史と信頼
菱田司法書士法人は、昭和8年に東京都品川区で創業し、昭和20年から現在の東京都大田区へと拠点を移し、90年以上にわたって地域の皆さまと歩んできた司法書士法人です。長い歴史の中で、私たちは「街の法律家」として、多くの方々の相続、不動産登記、会社設立などの法律手続きをサポートしてきました。
こうした長年の実績が、私たちにとって何よりの財産です。特に相続に関しては、代々続くご家族の相続や不動産をめぐる複雑な登記など、世代を超えたご相談を多くお受けしています。地元で培ってきた信頼と経験こそが、初めてご相談いただくお客様にも安心してご依頼いただける理由の一つです。
さらに、法改正や税制の変更にも迅速に対応できる体制を整えており、時代に合わせたサービス提供が可能です。信頼は一朝一夕では築けません。菱田司法書士法人では、常に誠実な姿勢とわかりやすい説明を心がけ、安心と納得を提供することを第一に考えています。
地域密着のサービス
東京都大田区に根ざし、地域の皆さまとともに歩んできた私たちは、地域密着型のきめ細やかな対応を大切にしています。ご相談に訪れる方の多くが、大田区やその周辺エリアにお住まいで、「近くに信頼できる司法書士がいて助かった」とのお声をいただくことも少なくありません。
相続の問題は、時として複雑でナイーブな問題を含みます。だからこそ、地域事情をよく理解したうえで、お一人おひとりに合わせた柔軟な対応が必要です。菱田司法書士法人では、書類の手配や役所との調整なども含めて、地域のネットワークを活かしたスムーズな支援を行っています。
また、急ぎの対応が必要なケースにも迅速に対応できるのは、地元に事務所があるからこそ。お客様の立場に立ったサービスを心がけ、暮らしに寄り添った存在であり続けます。
専門家との連携
相続に関わる手続きは、司法書士だけで完結するものではありません。不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成だけでなく、相続税の申告には税理士の力が必要ですし、法的トラブルに発展する可能性があれば弁護士との連携も欠かせません。
菱田司法書士法人では、税理士・弁護士・不動産会社・生命保険会社・行政書士など、各分野の信頼できる専門家と連携しています。それにより、相続全体をワンストップで支援する体制を構築しています。
お客様にとって、複数の専門家を個別に探し、依頼し、説明するのは大きな負担です。私たちが橋渡しとなることで、手間と時間を減らし、精神的なご負担も軽減できるのです。これは、菱田司法書士法人だからこそ提供できる、包括的なサービスです。
お客様への寄り添い
私たちが最も大切にしているのは、「相談してよかった」と思っていただけることです。法律の手続きや専門用語に不安を感じる方も多い中で、菱田司法書士法人では、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することを心がけています。
また、相続という場面では、家族や親族間の感情的な葛藤が生じることもあります。その際も、冷静かつ中立の立場からアドバイスを行い、お客様が納得できる選択を一緒に考えていきます。大切なのは、手続きの「正確さ」だけでなく、「気持ちに寄り添った対応」であると私たちは考えています。
一度ご相談いただいた方から、別のご親族やご友人をご紹介いただくことも多く、信頼の輪が地域の中で広がっています。これは、単なる事務処理だけでなく、人と人とのつながりを大切にしてきた結果です。
実績と事例紹介
これまでに菱田司法書士法人が対応してきた相続案件は数千件にのぼります。たとえば、相続人が多数にわたり所在が不明なケースでも、戸籍の徹底調査や関係者への連絡を通じて、最終的に登記を完了させた実績があります。
また、相続財産の中に共有持分の不動産が含まれ、遺産分割協議が難航したケースでは、税理士と協力して分割と税負担のバランスを考慮し、円満な解決を導きました。こうした複雑な事例にも対応できるのは、長年の経験と他士業との連携によるものです。
お客様からは、「最初は不安だったけれど、一つひとつ丁寧に進めてくれて助かった」「遠方に住んでいたが、オンライン対応でも安心できた」といった声を多数いただいています。そうしたお声が、私たちの原動力です。
相続手続きの具体的なサポート内容

相続登記のサポート
不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きが「相続登記」です。
2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由がなく3年以内に登記をしなかった場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。この制度改正により、相続登記の重要性はますます高まりました。
菱田司法書士法人では、相続登記に必要な戸籍の収集から申請書の作成、法務局への提出までをワンストップで代行しています。不動産の評価額や所在地が複数にまたがる場合も、専門的な知識をもとに的確な判断と手続きを行います。
また、「どの不動産が相続対象なのかが分からない」「共有名義になっていて困っている」といったご相談にも丁寧に対応します。名寄帳や登記事項証明書を取得し、財産内容の把握から支援いたします。
不動産が複雑な場合でも安心してお任せください。
特に相続人が複数いるケースでは、遺産分割協議書の作成と併せて進める必要があり、専門的なサポートが重要です。私たちはお客様が確実に法的権利を取得できるよう、責任を持ってサポートいたします。
遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合、「誰がどの財産を受け取るか」を話し合いで決める必要があります。
これが「遺産分割協議」であり、その内容を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
協議書がなければ、不動産や預貯金などの名義変更は行えません。
菱田司法書士法人では、公平かつ法律的に有効な形で協議書を作成するサポートを行っています。
相続人全員の同意が必要となるため、相続人調査(戸籍調査)も同時に進め、抜け漏れのないよう丁寧に対応します。
また、相続人間での意見の相違やトラブルが予想される場合には、第三者の立場から冷静なアドバイスも可能です。
感情的な対立を防ぎ、将来的な争いを避けるためにも、司法書士の介在が非常に有効です。
形式的に整った協議書を作成するだけでなく、実務的に使える書面として仕上げます。
金融機関や法務局に提出する際に不備が出ないよう、確かな書類作成を行いますので安心してお任せください。
相続税申告の支援
相続税の申告が必要となるかどうかは、相続財産の総額によって決まります。
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産がある場合、相続開始から10か月以内に税務署へ申告・納税しなければなりません。
菱田司法書士法人では、提携税理士と連携し、相続税の申告が必要な方へのサポートも充実しています。
税務署に対して正しく評価・申告するためには、不動産の路線価評価、非上場株式の評価、相続人間での納税分配など、非常に高度な知識が求められます。
相続税は適切に控除や特例を使うことで、節税につなげることも可能です。
例えば小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生前贈与との併用など、個別の事情に応じたアドバイスを行い、無駄のない納税をご提案いたします。
税理士との連携により、法的手続きと税務申告が一体化された安心の体制で、スムーズな相続を実現します。
遺言書作成のアドバイス
相続でのトラブルを未然に防ぐ有効な手段の一つが「遺言書の作成」です。
特に、「子どもがいない夫婦」「再婚同士の家族」「特定の相続人に多く残したい場合」などでは、明確な意思表示がなければ争いのもとになります。
菱田司法書士法人では、遺言書の作成に関する法的アドバイスや文案の作成支援を行っています。自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれのメリット・デメリットを説明し、ご本人の状況に合わせた方法をご提案します。
また、遺言書をどこに保管するか、誰に知らせておくかといった「残し方」の部分も重要です。
相続人が遺言の存在に気づかず、法定相続で進んでしまうケースもあるため、生前から司法書士に相談しておくことで、確実な実行へとつながります。
「遺言を考えるのはまだ早い」と思っている方も、一度だけでもご相談ください。
ご自身の大切な資産を、思い描いた通りに託すために、今からできる準備があります。
その他のサポート
菱田司法書士法人では、上記以外にも相続に関わるさまざまな手続きをトータルでサポートしています。
たとえば以下のような場面でも、ご相談を承っています。
- 預金口座の解約や払戻し手続き
- 株式・有価証券の名義変更
- 不動産の売却サポート(提携業者との連携)
- 相続放棄や限定承認の家庭裁判所申立て
- 家族信託や成年後見制度の活用提案
「何を、誰に、どこまで頼めばいいか分からない」——そんな時こそ、私たちの出番です。
菱田司法書士法人では、司法書士の専門性を核に、税理士・弁護士・不動産会社などとのネットワークを駆使し、最適なルートを設計します。
相続は一生のうち何度も経験するものではありません。だからこそ、確実に・安全に・気持ちよく手続きを終えることが大切です。
お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
相続に関するよくあるご質問と回答

相続手続きの期限は?
相続手続きにはいくつかの重要な期限があり、それを過ぎると不利益を被る可能性があります。
まず、相続放棄や限定承認を行う場合の申述期限は、相続の開始を知ってから3か月以内と定められています。この「開始を知った時」とは、被相続人が亡くなった日ではなく、実際にその死を知った日を基準にします。この3か月の間に、遺産の内容を調査し、相続するか放棄するかを判断する必要があります。
また、相続税の申告と納税には10か月という期限があります。これは被相続人が亡くなった日から起算し、相続人が複数いても全体としてひとつの申告期限となるため、早めに準備を始めることが大切です。
さらに、2024年から施行された法改正により、相続登記は相続の開始を知った日から3年以内に行うことが義務付けられ、違反すると10万円以下の過料が科される可能性もあります。
このように、相続は放置すればするほどリスクが増大するため、早期の対応が極めて重要です。 菱田司法書士法人では、こうした期限に関する注意点を一つひとつ丁寧にご説明し、確実なスケジュール管理のもとで手続きをサポートしています。
相続放棄の方法は?
相続放棄とは、被相続人の財産や負債の一切を相続しないという意思を法的に表明する手続きです。
相続放棄を希望する場合は、家庭裁判所に対して所定の申述を行う必要があり、単に「何も受け取らない」と相続人同士で話し合っただけでは効力がありません。
申述書の作成には、戸籍謄本・住民票・被相続人の除籍謄本などの書類が必要となります。また、提出後に家庭裁判所から照会書が届き、それに対して回答しなければ正式な受理とはなりません。
注意すべきは、一度相続放棄をしてしまうと撤回は原則としてできないという点です。 そのため、被相続人の財産や借金の状況をよく調べたうえで判断することが重要です。
菱田司法書士法人では、放棄すべきかどうかの判断材料を一緒に整理し、家庭裁判所への提出書類も含めて手続きを代行しています。「負債があるか不安」「財産内容が見えにくい」といったご相談にも、適切に対応いたします。
相続税の納付方法は?
相続税の納付は、現金一括払いが原則とされています。
しかし、財産の大部分が不動産などすぐに現金化できない資産で構成されている場合、納税資金の確保に悩まれる方も少なくありません。
そうした場合には、「延納」または「物納」といった制度の利用が検討できます。
延納は、税務署の許可を受けることで数年にわたって分割で納付する方法です。一定の利子税がかかるものの、負担を分散することが可能であり、相続税の納税が困難な方にとっては有効な手段です。
また、物納は不動産などの資産をそのまま納税に充てる方法ですが、要件が厳しく、税務署の審査をクリアする必要があります。
菱田司法書士法人では、提携税理士と連携し、納税方法の選択に関するアドバイスや必要書類の準備を総合的にサポートいたします。
「不動産しか相続していない」「手元に現金がない」といった方も、安心してご相談ください。
遺言書がない場合の対応は?
被相続人が遺言書を残していない場合、相続は「法定相続人全員の合意」によって進められます。
これを「遺産分割協議」と呼び、誰が何を相続するかを話し合いで決定しなければなりません。この協議が成立しなければ、名義変更や財産分配は一切進められません。
相続人の数が多い場合や、相続人間に疎遠・不仲がある場合には、協議が長期化し、感情的なトラブルに発展することも少なくありません。
そうした事態を避けるため、菱田司法書士法人では、中立的な立場から法律に則ったアドバイスと文書作成を行い、話し合いが円滑に進むようサポートしています。
また、遺言書がないことで法定相続人の範囲や相続割合が複雑になるケースにも対応。 相続関係図や戸籍収集をもとに、的確な対応をご提案いたします。
相続人が複数いる場合の手続きは?
相続人が複数いる場合には、相続財産を「誰が、何を、どのように」相続するかを明確に決める必要があります。
その際に必要となるのが「遺産分割協議」と、その内容を書面にした「遺産分割協議書」です。相続人全員の合意がなければ無効とされるため、全員からの署名・押印が不可欠です。
相続人の中に遠方に住んでいる方や、所在不明の方がいる場合には、戸籍や住民票の追跡調査が必要になることもあります。また、認知症などの理由で意思表示が困難な相続人がいる場合は、家庭裁判所での成年後見制度の利用が必要になります。
菱田司法書士法人では、こうした複雑な相続関係にも対応可能な体制を整えており、相続人間の調整や連絡、書類の整備まで一括でサポートしています。
相続人が複数いて、誰に何をどう渡すかに悩んだら、まずは私たちにご相談ください。
菱田司法書士法人への相談方法

相談の流れ
相続に関するご相談は、菱田司法書士法人でスムーズに進めることができます。
まずは、お電話またはホームページの問い合わせフォームからご連絡ください。初回のご連絡時には、お名前・ご相談内容の概要・希望する面談方法(来所またはオンライン)をお伺いします。
次に、実際のご相談日程を調整し、司法書士との面談を通じて現在の状況やお悩みをしっかりとヒアリングいたします。
このときに、相続人の構成や財産内容、遺言の有無などを確認させていただくため、可能な範囲で資料をご準備いただくとスムーズです。
面談後は、必要な手続きの全体像をわかりやすくご説明し、今後の進め方や費用見積りをご提示します。
その内容にご納得いただいたうえで、ご依頼の手続きを進めてまいります。ご相談だけで終えることももちろん可能ですので、「まず話だけ聞きたい」という方も遠慮なくご連絡ください。
相続手続きは「相談するのが遅かった」と後悔するケースが多くあります。
だからこそ、早めの一歩を、私たちは全力で応援しています。
相談時の持ち物
ご相談時には、状況確認のためにいくつかの書類をご持参いただけると、より具体的なアドバイスが可能となります。
たとえば以下のような書類です:
- 被相続人の死亡が確認できる書類(死亡診断書のコピーや除籍謄本など)
- 相続人の関係性がわかる戸籍謄本類(可能な範囲で)
- 不動産の登記簿謄本や固定資産税通知書
- 預貯金の通帳コピー、証券残高一覧
- 遺言書(ある場合)
上記がすべて揃っていなくても問題ありません。
資料が足りない場合でも、菱田司法書士法人で必要書類の取得代行を行っております。「何を持っていけばよいかわからない」という場合でも、事前にお電話でご案内いたしますので、ご安心ください。
安心のご提案と柔軟な対応
相続のご相談は、誰にとっても初めてで不安がつきものです。
菱田司法書士法人では、お客様が安心してご相談いただけるように、事前に手続きの流れや必要となる作業をしっかりご説明し、その上でご希望やご予算に合わせた対応をご提案しています。
ご相談の内容やご家庭の事情によって必要な手続きは異なります。だからこそ、画一的な対応ではなく、お一人おひとりに合わせた柔軟なご提案を大切にしています。
たとえば、
- 手続きはすべて専門家に任せたい方
- ご自身でできることは進めながら一部だけ専門家に依頼したい方
- 相続税がかかるかどうかだけ判断したい方
など、それぞれの状況に応じたサポートを分かりやすくご案内いたします。
費用のご説明も、明確で誠実なコミュニケーションを心がけておりますので、ご不明な点があればいつでもお尋ねください。
まずは「相談すること」からが相続の第一歩。
無理に契約を勧めることは一切ありませんので、どうぞ安心してご連絡ください。
オンライン相談の可否
遠方にお住まいの方や、お仕事で時間が取りにくい方のために、オンライン相談も積極的に行っております。
ZoomやGoogle Meetなどのツールを使ったビデオ通話に対応しており、書類の確認や手続きの流れの説明も、画面共有などを通じて丁寧にご案内いたします。
また、メールや郵送を併用することで、来所が難しい方でも一通りの相続手続きを完結可能です。
実際に、海外在住のお客様や地方にお住まいのご相続人とのやり取りも多数実績があります。
ご希望に応じて柔軟に対応いたしますので、「対面が不安」「移動が難しい」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
相談後のサポート体制
ご相談・ご依頼後は、専任担当が一貫して対応し、お客様にとって最も効率的な手続きをサポートいたします。
例えば、
- 書類収集の代行(戸籍・住民票・登記簿など)
- 相続関係説明図の作成
- 相続人間の連絡サポート
- 提携税理士・弁護士・不動産会社の紹介と連携
- 完了報告とアフターフォロー
まで、一つひとつ丁寧に対応いたします。
また、手続き完了後も、「他の家族の相続でも再度お願いしたい」とご依頼いただくことも多く、お客様との長い信頼関係を築いていけるよう努めています。
一度のご相談が、将来にわたる安心と信頼につながる。
それが私たち菱田司法書士法人の目指すサービスです。
Q&A よくあるご質問にお答えします

Q1. 相続の相談はいつ頃から始めるべきですか?
できるだけ早くご相談いただくのが理想です。
被相続人が亡くなる前でも、「財産の整理をしたい」「将来の相続に備えたい」というご相談が増えています。生前から準備しておくことで、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
Q2. 相続税がかかるかどうかは誰に相談すればいいですか?
相続税については税理士が専門です。
ただし、菱田司法書士法人では提携税理士と連携していますので、「税金がかかるのか知りたい」という段階からご相談いただければ、必要に応じて税理士をご紹介し、スムーズに対応できます。
Q3. 相続登記の義務化とは何ですか?
2024年4月から相続登記は義務となり、3年以内の手続きが必要になりました。
これを怠ると10万円以下の過料の対象となるため、相続が発生したらなるべく早めにご相談いただくことをおすすめします。
Q4. 親が認知症で遺産分割の話し合いができないのですが?
その場合は家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任する必要があります。
ご本人の判断能力が不十分な状態での協議は無効になるため、正しい手続きを踏むことが重要です。菱田司法書士法人では後見手続きについてもご相談可能です。
Q5. 兄弟で揉めています。司法書士に仲裁してもらえますか?
司法書士は中立的な立場から法的助言を行うことが可能です。
ただし、明確な対立や訴訟リスクがある場合は、弁護士との連携が必要です。状況に応じて、提携の弁護士をご紹介することもできますのでご安心ください。
Q6. 土地が遠方にある場合でも依頼できますか?
はい、全国の不動産登記に対応可能です。
たとえ不動産が他県にあっても、当法人が必要書類の取り寄せや手続きを代行できます。郵送・オンラインでのやり取りも可能です。
Q7. すべての手続きをまとめてお願いできますか?
はい、相続に関わる手続きを一括でご依頼いただけます。
相続登記・遺産分割協議書の作成・相続関係図の作成・税理士の紹介まで、菱田司法書士法人が窓口となり、すべての手続きを取りまとめて対応いたします。
まとめ

相続は誰にでも訪れる現実であり、同時に大きな法的・実務的負担を伴うものです。
戸惑いや不安を抱えながら手続きを進める中で、「誰に相談すればいいのか」「どこから始めればいいのか」と立ち止まってしまう方も少なくありません。
そんな時に頼りになるのが、法律と実務に精通した司法書士の存在です。
菱田司法書士法人では、東京都大田区に根差し、相続に関わる登記・書類作成・専門家連携を通じて、皆さまの不安を解消するための総合的なサポートを提供しています。
また、必要に応じて税理士や弁護士とも連携し、「相続登記だけで終わらない」包括的な支援を行っています。相続の状況は一人ひとり異なるからこそ、画一的な対応ではなく、お客様に寄り添ったオーダーメイドの提案を大切にしています。
相続・司法書士・税理士に関するご相談は、どんな些細なことでもかまいません。
「何か起こってから」ではなく、「今できること」を一緒に考えましょう。あなたの大切な財産とご家族の未来を守るために、ぜひ私たちにお手伝いさせてください。
東京都大田区で相続のご相談なら、どうぞ安心して菱田司法書士法人までお問い合わせください。